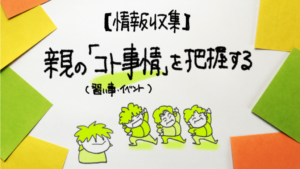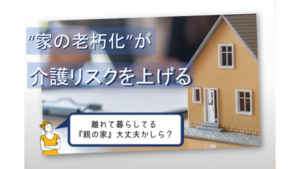介護がラクになる!家庭でできる〇〇セラピーの工夫

「相手の気持ちが安定せず、こっちもしんどい」──そんな日が続く前に
老いの中には、薬ではどうにもならないつらさや痛みがあります。
身体の不調だけでなく、孤独や不安、焦りといった“こころの痛み”――
そうした感情は、時に怒りや無気力となって現れ、周囲の人を戸惑わせます。そんな日が続くと、「こっちのほうが参ってしまう」と感じてしまうのは、当然のことです。
そのつらさは、あなたのせいではありません。「仕方ない」と流すだけでは、しんどさがたまってしまうこともあるでしょう。
今回は少し立ち止まって、「親の気分が穏やかになる仕掛けづくり」に目を向けてみたいと思います。
介護の大変さは、相手のつらさをそばで感じ続けることから生まれる
介護のしんどさは、単に身体的な負担だけではありません。
むしろ多くの人が感じているのは、相手の不機嫌さや感情の揺れにどう対応すればよいかわからない、という精神的な疲労ではないでしょうか。
親が不安定でイライラしていると、こちらも気持ちが揺れてしまう。無意識のうちに、相手のつらさが自分に“伝染”してしまう。
そんな中で、自分を責めたり、我慢しすぎたりしてしまう人も少なくありません。
だからこそ、「親の心が落ち着く時間」を増やす工夫が、自分自身をラクにする第一歩にもなるのです。
ここからは、介護のつらさをやわらげ、乗り越えていくための手がかりになりうる多様な「セラピー」をご紹介していきます。
音楽・アロマ・園芸…こんなにある〇〇セラピー!
近年、薬を使わずに症状を和らげたり、生活の質(QOL)を高めたりする「セラピー」が注目されています。
調べてみると、その種類は思った以上に多彩です。
たとえば、次のようなものがあります。
🐶 アニマルセラピー:動物とふれあうことで心が癒され、安心感や喜びを得られる療法。
🐠 アクアリウムセラピー:水槽の魚を眺めることで気持ちが落ち着き、ストレス軽減につながる療法。
🌸 アロマテラピー:香りを使って心身のリラックスや気分転換を促す療法。
🤲 タッチケア/タクティールケア:やさしい手のふれあいで安心感やぬくもりを伝え、不安を和らげるケア。
🎶 音楽療法:音楽を聴いたり演奏したりすることで感情の安定や交流を促す療法。
🎨 芸術療法:絵を描くなどの創作活動を通じて、感情の表現や心の整理を助ける療法。
🌱 園芸療法:植物を育てたり触れたりすることで、季節を感じ、心身を整える療法。
🛍️ 買い物療法:商品を選ぶ・支払うといった日常的行動で、生活意欲や判断力を引き出す療法。
💄 化粧療法:身だしなみを整えることで、自分らしさや社会とのつながりを回復させる療法。
🪆 箱庭療法:砂の入った箱にミニチュアを配置し、自分の内面を表現・整理する療法。
📸 回想療法:昔の写真や思い出話を通じて、自己肯定感や人とのつながりを取り戻す療法。
🕊️ ディグニティセラピー:人生の意味や大切にしてきたことを言葉にすることで、存在の意義を支える対話の療法。
身近なものに意識を向けて活かせば、穏やかなひとときが作れる!
これらのセラピーの中には専門的な知識が求められるものもありますが、身近な工夫で、家庭でも気軽に取り入れられるものも多くあります。
たとえば
📻 ラジオを流してみる(音楽療法)
🧴 お気に入りの香りのハンドクリームを使ってみる(タッチケア、化粧療法)
🌱 小さな鉢植えをテーブルに置いてみる(園芸療法)
などなど……。
特別な準備がなくても、感情の安定や生活リズムを整える助けになることがあります。
うまくやることが目的ではありません。たとえば、植物がうまく育たなかったとしても、その過程の中に心の動きが生まれること自体が、良い刺激になるのです。
まずは、あなたが「ちょっとやってみたい」と思えるセラピーから、始めてみませんか。
小さな工夫がもたらす穏やかな時間は、お互いのためになる
介護される側が心地よく過ごせると、介護する側にとっても心がラクになります。
セラピーの効き目はすぐに出るとは限りませんが、ちょっとした変化や笑顔が見えると、きっとあなたの心もほぐれていくことでしょう。
工夫を仕掛けること自体が気分転換になることもありますし、誰かのためにと思って始めたことが、いつの間にか、あなた自身を癒してくれる時間になるかもしれません。
介護の時間を、ただの「苦労」にしないために。
小さな工夫が、優しいぬくもりのあるひと時に、そしてあなた自身の余裕につながっていきますように。
この記事を書いた人
介護支援専門員(ケアマネジャー)・介護福祉士
京都大学卒業後、介護福祉士として、介護老人保健施設・小規模多機能型居宅介護・訪問介護(ヘルパー)の現場に従事。その後、育休中に取得した介護支援専門員の資格を活かし、居宅ケアマネジャーのキャリアを積む。「地域ぐるみの介護」と「納得のいく看取り」を志している。