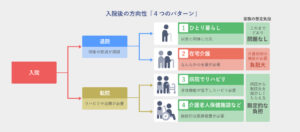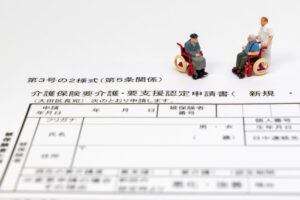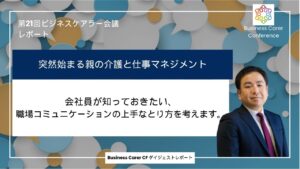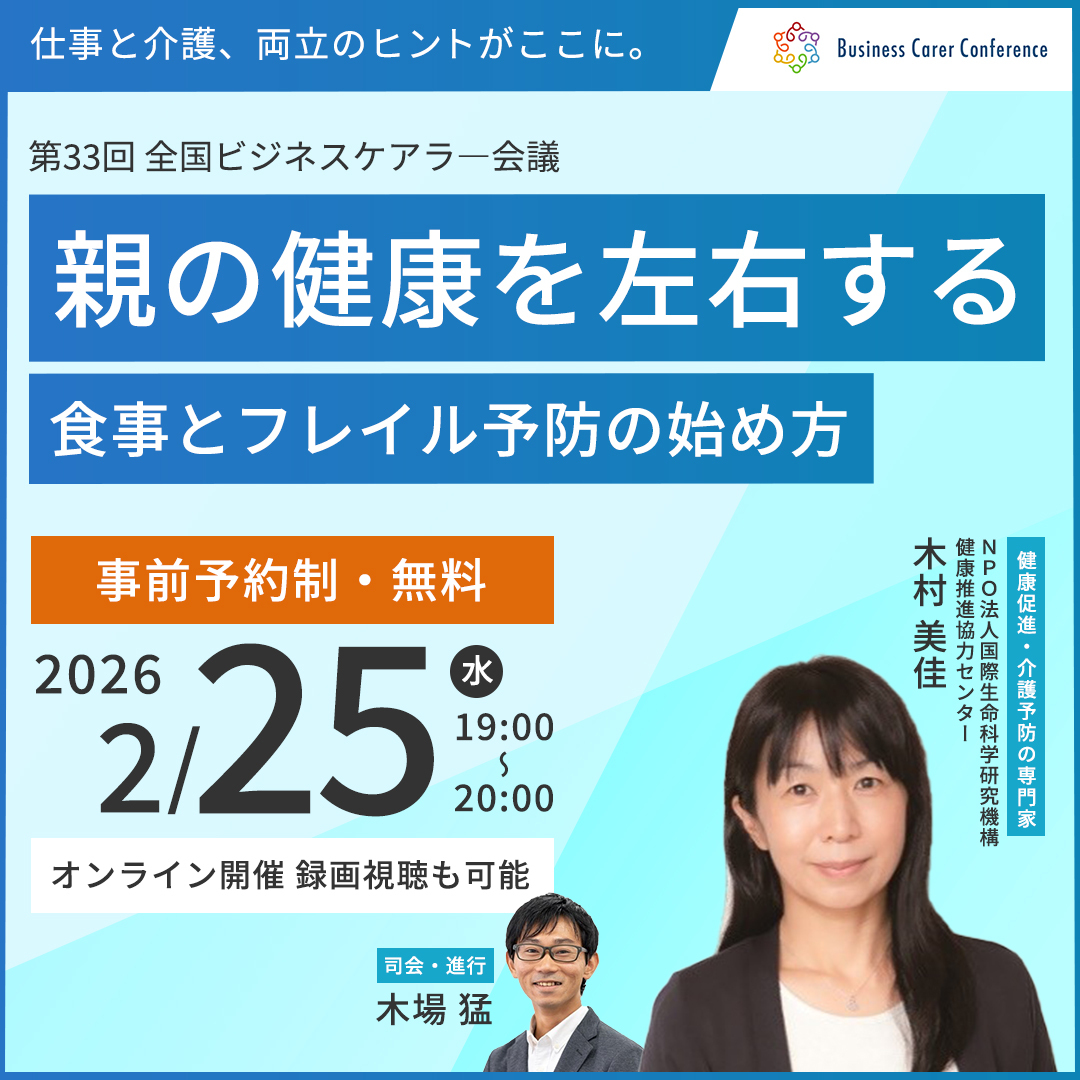ここから始めるのが大正解!親の老後の備えファーストステップ

「まだ早い」と思っている方にも自宅で簡単準備!
「エンディングノートなんて縁起でもない」「介護の話をしたら怒られそう」
そう感じて、親の老後について何も話し合えていないまま時間だけが過ぎている。こんなことはありませんか?
そんなあなたに、今こそ気軽に始めて欲しい「これからの準備」をお届けします。
大切なのは「全部を話し合う」のではなく、「生活の延長でできることから動いてみる」こと。介護を見据えた準備というと構えてしまいますが、実はスマホの設定ひとつから始められるんです。
親のスマホに緊急連絡先を登録
まずおすすめなのが、親のスマートフォンに【緊急時情報】を登録しておくことです。
これは万が一、親が外出先やひとりの時に倒れてしまったときなど、スマホのロックを解除できなくても、第三者が緊急時に連絡できるようにするための設定です。
たとえば、救急隊が駆けつけた際に、スマホがロックされていても、暗証番号や指紋認証がわからなくても、あらかじめ登録しておいた連絡先に通報できます。もしもの時、本人が話せない状態でも家族や近しい人に早く知らせてもらえる——そんな“命をつなぐ設定”と言えます。
この機能はiPhoneなら「メディカルID」、Androidなら「緊急時情報」から簡単に設定できます。登録できる情報は以下のような内容です。
- 緊急連絡先
- 基礎疾患や服薬情報
- アレルギーの有無
- 血液型
※機種やOSのバージョンによって表示の場所や操作手順が少し異なることがありますので、わからない場合はスマホの「設定」アプリから「緊急」などのキーワードで検索してみてください。
緊急連絡先には、初動で動ける人を入れておくのがおすすめです。遠方にいてすぐに駆けつけられない人に連絡がいってしまうと、不安がらせてしまうだけになることがあるからです。たとえば、一緒に住んでいる家族や、近所に住む兄弟など、「最初に現場で対応できる人」を選んでおくと安心です。
「何かあったら困るから、これだけはやっておこうよ」と伝えると、親も納得しやすいものです。「こんなことができるらしいから、登録しておくといいかもよ」といった軽い声かけでも十分です。
スマホの操作に不安がある場合は、「ちょっと見てくれる?」と親から声をかけてくるかもしれません。逆に、あなたから「一緒にやってみようか?」と声をかけるのもよいでしょう。
一緒に画面を確認しながら進めれば、自然と親子の結びつきを強くする時間にもなります。ただのスマホ設定のようでいて、こうしたやりとりはふだんは話しにくいことを共有しやすくしてくれる土台にもなっていきます。
このように、スマホの緊急時登録は、“介護”という言葉をあえて出さなくても、緊急時の備えというニュートラルな話題から自然に始められるアクションです。
ぜひここから一歩踏み出して、今日という日を「親と一緒に、介護に備え始めた記念日」にしてみてくださいね。
自分のスマホには地域包括支援センターの電話番号も登録
緊急時情報とは別に、スマホで簡単にできる準備として、もうひとつおすすめがあります。それは、自分のスマホの電話帳に、地域包括支援センターの連絡先を登録しておくことです。
地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを支える公的な総合相談窓口で、全国すべての市区町村に必ずひとつ以上設置されています。
それってどこにあるの…?と思われる方もいるかもしれませんが、面倒なことは何もありません。
以下のリンクから、親の住んでいる住所を入力して検索し、最寄りの地域包括支援センターの電話番号を、自分のスマホの電話帳に登録しておくだけでOKです。
介護は、突然始まることもあれば、じわじわと生活の中で始まっていくこともあります。「最近、買い物が大変そう」「掃除がおっくうになってきたみたい」など、小さな気づきから不安を感じたとき、その段階から気軽に無料で相談できるのが、地域包括支援センターです。介護が本格化する前に相談することで、後々の負担や混乱を減らすことができます。
こうして「困ったとき、誰に聞けばいいか」をあらかじめ知って連絡先を控えておくだけで、まだ見ぬ介護の不安はぐっと小さくなるはずです。
【関連ページ】地域包括支援センターとは?役割や相談できることについてわかりやすく解説
次のステップは元気なうちに始める『お金の備え』
ここまでの備えを進めて、まだ余力がある方は、お金に関する準備にも少しだけ目を向けてみましょう。
とはいえ、遺言や相続といった重たい話ではありません。ここでのポイントは、「いざというときに、家族が手続きを代行できるようにしておくこと」です。
たとえば、銀行によっては、以下のような仕組みを設けていて、比較的かんたんに、しかも無料で手続きできる場合があります。
※名称や利用条件は金融機関ごとに異なりますので、詳しくは各行の窓口でご確認ください。
代理人カード
あらかじめ指定された家族が、本人に代わって入出金や残高照会を行える制度です。親に判断能力があるうちに発行・利用できるため、急な入院や外出困難な状況でも、生活資金の出し入れが滞らずに済みます。
<こんなケースで役立ちます>
・夫婦で一つの口座ATMから預入引出をしたいとき
・親が入院して銀行に行けないとき
・親の足腰が弱ったり、体調が悪く「代わりに行ってほしい」と頼まれたとき
予約型代理人サービス
事前に手続きをしておくことで、将来、認知症などにより判断能力が低下した場合でも、代理人が診断書などを提出すれば、預金の引き出しや支払いを代理人が行えるようになる制度です。
<こんなケースで役立ちます>
・認知症や脳血管障害になり、意思表示が難しくなったとき
・元気なうちは第三者に資産状況を知られず通常通りの取引をしたいとき
2つの制度の違いをシンプルに言えば、『代理人カードは「今の不便をサポート」する仕組み、予約型代理人サービスは「将来の判断力低下に備える」ための制度』です。親が急に入院して預金を動かせない——そんな事態は意外と身近です。そのような時、あらかじめこのような代理人登録をしておくと、慌てずにスムーズに対応できます。
これらのサービスは、親が元気で判断能力がしっかりしている今だからこそ利用できる仕組みです。ですから、思い立った“その時”に動くことができればベスト。済んでしまえばほんの少しの工夫ですが、将来的には大きな心強い備えになります。
お金の話はどうしても切り出しにくいものですが、こんなふうに切り出してみるのはいかがでしょうか。
「今こういう制度、注目されてるんだって。手続きも難しくないし、元気な今のうちしかできないらしいよ。まずは、今使ってる銀行で取り扱いがあるか調べてみようよ。」
「今注目されている」「元気なうちしかできない」と聞くと、なんとなく気になりますよね。その流れに任せれば気負わずに、今後のお金の話にも触れることができるかもしれません。
言いにくいことは、生活の延長からゆるやかに始めよう
親の老後について話すのは、たしかに気まずさを感じることもあるかもしれません。
でも、すべてをいきなり話し合う必要はないのです。
日常の中で、無理なくできることからひとつずつ。
押しつけではなく、“ちょっとお得な情報に乗ってみた”くらいの軽やかな気持ちで十分です。
その小さな積み重ねが、親との関係を守りながら、未来への備えにつながっていきます。
気づけばあなたも、介護準備の大きな一歩を踏み出していますように、応援しています!
この記事を書いた人
 岩瀬 良子(いわせ・りょうこ)
岩瀬 良子(いわせ・りょうこ)
介護支援専門員(ケアマネジャー)/介護福祉士
京都大学卒業。病院・施設・在宅など多様な現場に従事し、英国ホスピス視察などを経て「地域ケア」と「納得のいく看取り」を探求・実践する。
現在はその知見を活かし、「仕事と介護の両立」に関する個別相談やQ&A対応、専門記事の編集を担当。現場のリアリティと専門知識に基づいた、正確で温かみのある情報発信を行っている。
【執筆協力】中央法規出版『生活援助従事者研修 公式テキスト』