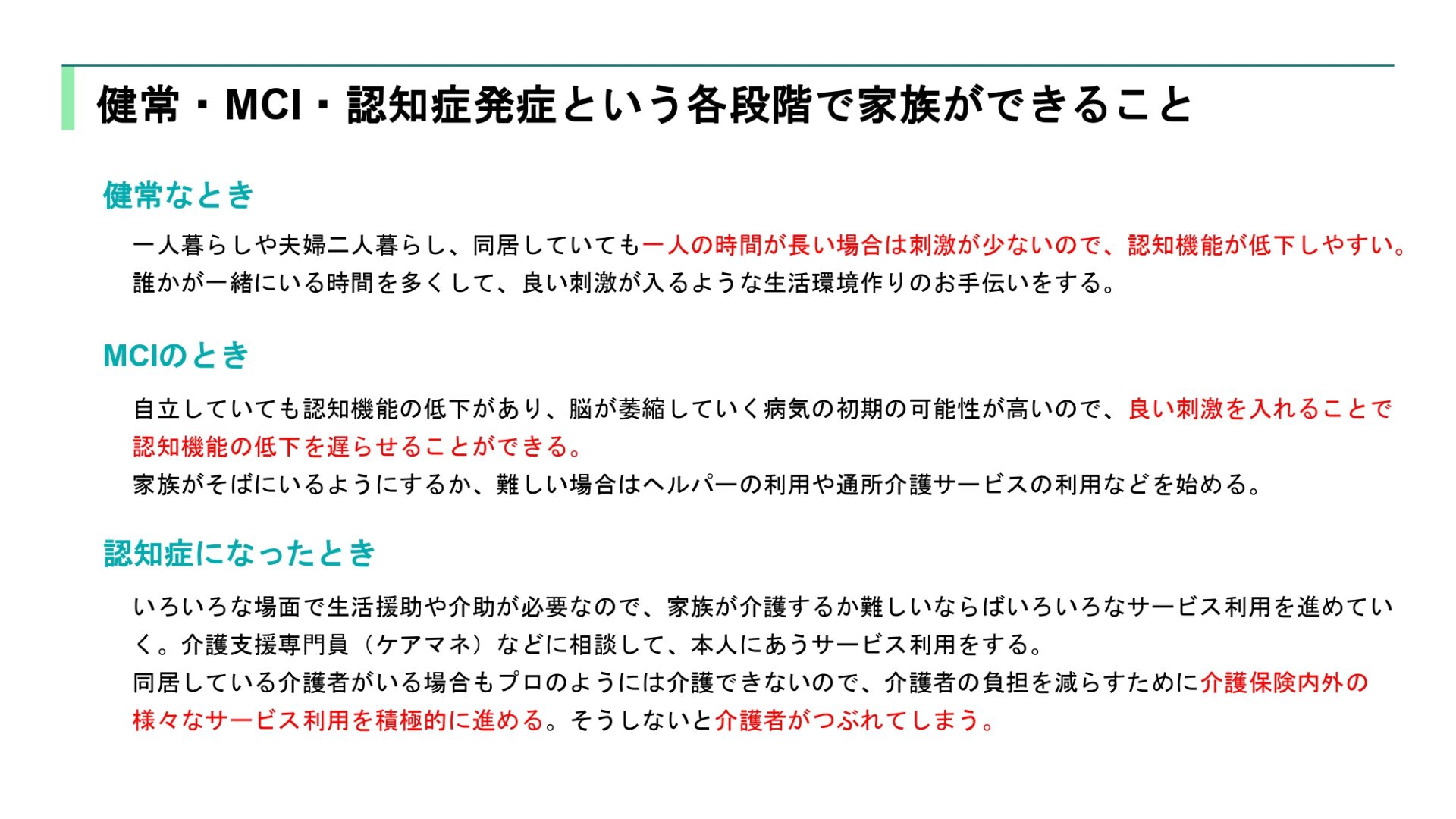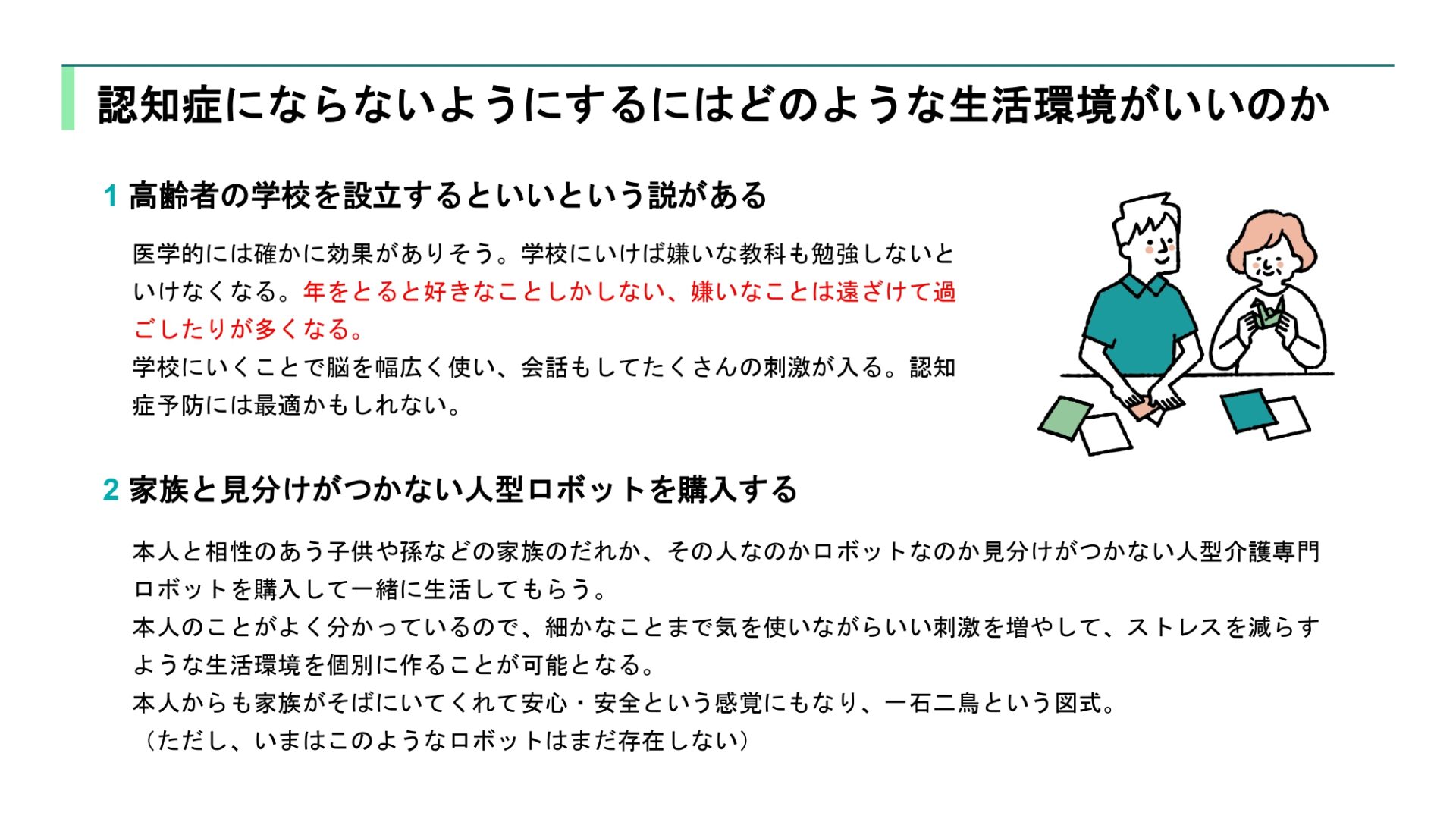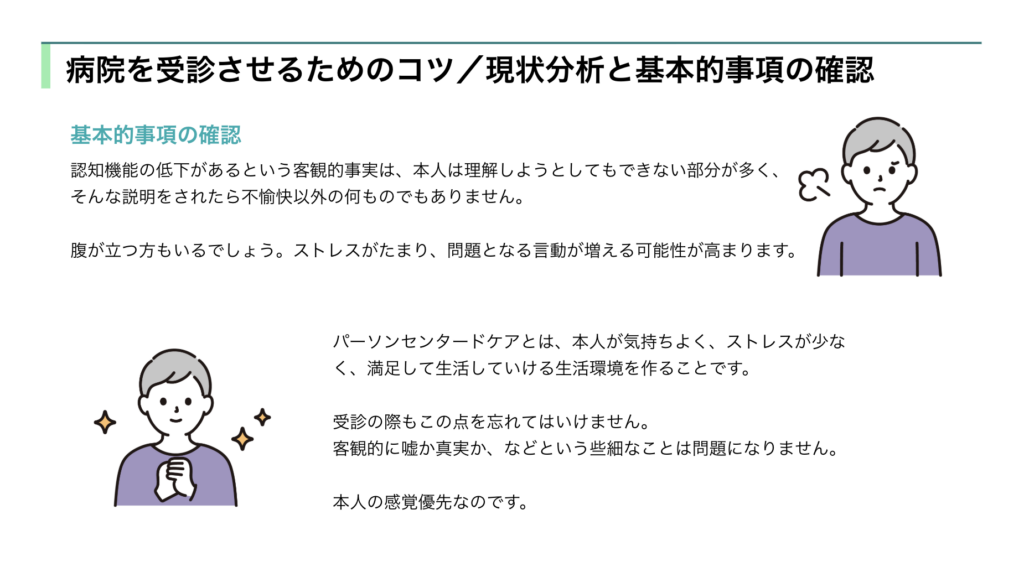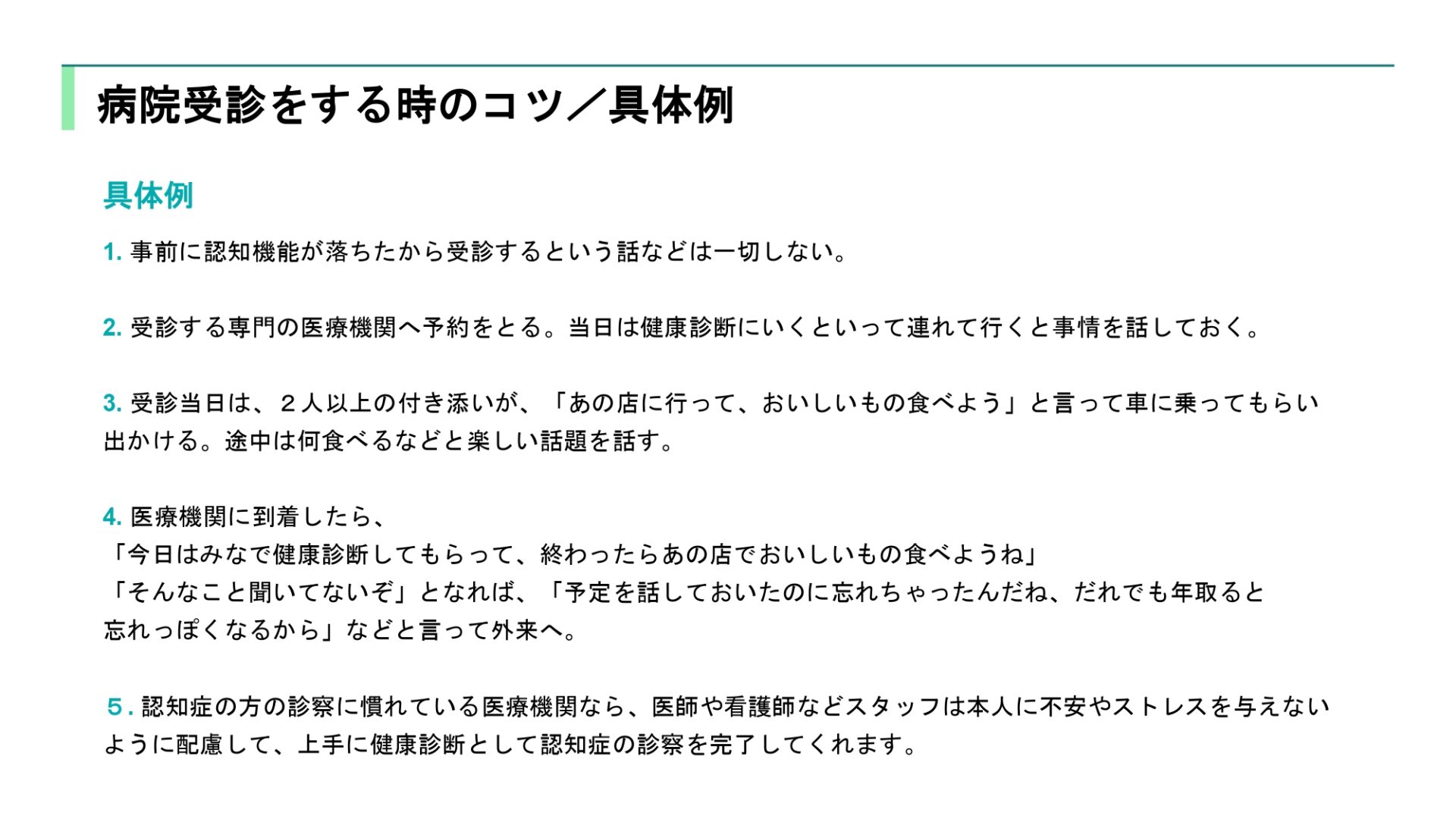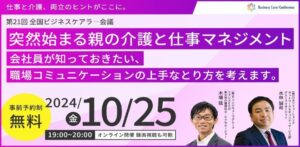認知症リスクにどう備える? 早期発見のポイントと予防法を医師が解説(後半)

ログインすることで、
ご視聴いただけます。
はじめに
2025年7月16日、リクシスは、第29回『全国ビジネスケアラー会議』を開催いたしました。
これから高齢社会がより一層加速し、仕事と介護の両立が当たり前の時代がやってきます。本オンラインセミナーは、高齢化の流れが加速する日本社会において、現役世代として働きつつ、同時にご家族の介護にも携わっている「ビジネスケアラー」の方々とその予備軍となる皆様に向けたセミナーです。
今回のテーマは「認知症の早期発見と予防方法」。
現代は高齢化が進んでいます。親や自分自身が認知症になる可能性を考えた方も少なくないでしょう。
実は、認知症の症状には段階があります。MCI(軽度認知障害)という認知症一歩手前の状態で早期発見できていれば、改善して認知症を予防することもできるのです。
今回は、現役の認知症専門医である医療法人さわらび会福祉村病院副院長の伊苅弘之氏をお招きし、MCIと認知症の見極めのポイントや認知機能の維持に効果的だと言われている生活や習慣について解説していただきました。
この記事では、
- 認知機能維持のために家族ができること
- 認知症の疑いのある家族に受診させるコツ
- パーソンセンタードケアとは
などのテーマでまとめています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①認知症リスクにどう備える? 早期発見のポイントと予防法を医師が解説(前半)
②認知症リスクにどう備える? 早期発見のポイントと予防法を医師が解説(後半)⇐このページのテーマ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
登壇者プロフィール
伊苅 弘之(いかり・ひろゆき)氏
医療法人さわらび会 福祉村病院 副院長
愛知県名古屋市出身。豊橋市に拠点を構える医療法人さわらび会福祉村病院副院長。医学博士。日本老年医学会・日本老年精神医学会の専門医・指導医。信州大学医学部卒業後、名古屋大学医学部老年科学教室に入局。記憶に関する基礎実験を行い医学博士を取得。1993年1月から1995年3月までアメリカ国立衛生研究所客員研究員。帰国後、名古屋大学医学部附属病院にて「ものわすれ、認知症外来」を5年間行う。1999年4月より高齢者のための総合的施設群(1,000人以上の高齢者が生活している)の中心となる福祉村病院に勤務。
認知機能維持のために家族ができること
各段階で、ご家族ができることについてお伝えいたします。
健常な時、一人暮らしや二人暮らしをしている時には、どうしても1人の時間が長くなってしまいます。どんどん積極的に会いに行ったり電話をしたりして、話す時間を増やしていきましょう。
難しい場合には、第三者、近所の方やお友達などを巻き込んで、いい刺激をいれるような生活を心がけてください。
心がけていても、MCIになってしまう方というのはいらっしゃいます。
MCIになると認知機能の低下が始まるのですが、周りの方は更にいい刺激をいれるよう積極的に行動してほしいです。難しい場合には、ヘルパーさんなど様々なサービスを利用すると良いでしょう。
MCIとは、ご自身で自立して基本的には援助がいらないという状態なのですが、その段階にあることを見過ごしていると、更に刺激が落ち続けて、認知機能も落ち、認知症へと進んでいきます。
認知症になると様々な援助や介助が必要になります。
ケアマネージャーさんがいらっしゃると思うので、積極的に在宅のサービスを増やして関われる人を増やしていきましょう。
介護者が近くにいる場合、自分だけが頑張るということはやめてください。介護者の負担は介護時間に正比例していきますので、どんどん負担が増えていきます。積極的にサービス利用を増やしていき、心にも体にも余裕を持つことが大切です。
認知症を予防する環境づくりのために考えられていること
認知症を絶対に予防できるという方法は、現在ありません。
脳に良い刺激を入れることで遅らせることができると言われていますが、それ以外にも様々な方法が言われています。
高齢者になったら学校に行くのが良いと言っている先生がいらっしゃいます。国語、算数、理科、社会、英語、体育、音楽、図画工作、美術など幅広くやると良いそうです。
人が集まりますので当然会話もありますし、刺激も入れることができますよね。
また、人間と見分けがつかないような高性能のロボットをそばに置くと良いと言っている先生もいらっしゃいます。
いつもそばにいて話しかけ、体調や食べ物のことを気にかけてくれる。今は人間がやっていることをロボットが認知症になる前からやってくれれば、認知症になる方は減るはずです。認知症になっても上手にケアしてくれて、認知機能の低下を予防して問題もおこりにくくなります。いまはそのような高性能のロボットは存在しませんが、将来的にはそういった未来がくるかもしれません。
病院を受診させるためのコツ
ご家族に認知症の疑いがある場合、病院を受診させるためのコツについてお話していきます。
「お父さん、物忘れがひどいから認知症になりかかってるかもしれない。病院に行こう」と言っても、そんなに悪くないから行きたくないと言われることがほとんどでしょう。
そういう方をどのようにして病院に連れて行くか、ということです。
まずは現状分析をします。
健常者に話すように説明をして、それで納得して連れていけるのであれば問題ありません。MCIの方やレビー小体型認知の方は、ちゃんと説明をすると行っていただける場合も多いです。
ですが、認知機能がすでに低下している状態ですと、自分の認知機能についても正確に把握することができず、ほとんどの方が心からたいしたことはないと思っています。もしくは、行くのが怖くて嫌だという方もいらっしゃるでしょう。
本人に正確で客観的に正しい事実をつきつけて、理解してもらい受診することを了解してもらうという行為は、実は、パーソンセンタードケアの視点からは大きく外れる行動になってしまうのです。
認知機能の低下という客観的事実は、本人が理解しようと思ってもできないことが多いですし、その説明をされても不愉快に思いストレスが溜まります。暴言や暴動など、問題となる行動が出てしまうこともあるでしょう。
パーソンセンタードケアとは、本人のストレスが少なく、満足して生活ができるように周りの方が配慮して接していくケアのことを言います。
大切なのは本人の感覚で、本人が幸せだなと思う方法を探す必要があるのです。
具体例
パーソンセンタードケアについての基礎知識を理解した上で、これからの具体例について聞いてください。
こういう方法もあるよ、というご紹介です。
まずは、認知機能が落ちたから受信する、というようなことはご本人に一切話さず、病院に予約をとります。予約の際、当日は健康診断に行くと言って連れ出すことも伝えてください。慣れている病院であれば、すぐに理解していただけます。
受診当日は、2人以上が付き添って出かけましょう。1人だと何かあった時に対処することが難しくなります。ご家族だけでなくても、ご家族とヘルパーさん、ご友人などでも大丈夫です。
そこで「何かおいしいものを食べよう」と言って出かけ、病院についたら「今日はみんなで健康診断をしてもらってからおいしいものを食べよう」と伝えます。
もし「そんなことは聞いてない」と言われたら、「ちゃんと伝えたのに、忘れちゃったかな」と言って外来へ向かいましょう。
認知症に慣れている医療機関であれば、スタッフの方が不安やストレスを与えず、上手に診察を完了してくれます。
客観的には嘘をついて騙して受診をさせていることになるのですが、ご本人の気持ちになれば快適に、ストレスなく診察を完了できたことになります。
ご本人のために、パーソンセンタードケアを上手に実施することが病院受診のコツ、ひいては認知症ケアの基本です。
認知症ケアを実施するには、様々なコツや工夫がいります。そういうようなことも聞いていただければ何でもお答えできますので、どうぞご活用ください。
参加者の皆さんへメッセージ
認知症というのは脳がだんだん縮んでいく病気ですが、誰がなるか、どうしたらなるかということはわかっていません。
ですが、どのような環境にいたらなりやすいのか・なりにくいかということはわかっているので、ぜひ皆さんもいい刺激を入れる、認知症になりにくい生活環境でお過ごしいただきたいと思います。
⇒親の介護費用とお金のリアル ~認知症による「資産凍結」を防ぐ対策をプロが解説~(前半)に戻る