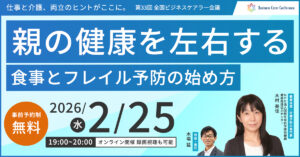子育てしながら“家族の介護を手伝う”ということ──30代パパのダブルケア体験記

子育てに追われる毎日の中で、気づけば家族の介護にも関わっていた──。
「全部を背負わなくても、自分なりにできる形で支えればいい」と語るのは、弊社の介護と仕事の両立相談員でもある36歳の佐々木元勝さん。
仕事と育児を続けながら副介護者として歩んできた、その体験をお届けします。
気づいたら“家族の介護を手伝っていた”──副介護者という立場
──最初から「介護をしている」という意識はありましたか?
佐々木元勝さん(以下、佐々木):全然なかったですね。介護が始まったのは今からちょうど10年前、僕が結婚して間もない頃でした。母方の祖母が自宅で転倒し、同居していた叔父も糖尿病や脳梗塞の後遺症で視力を失いがちで、祖母と一緒にケアが必要になったんです。
そんなある日、母から「仕事を辞めたい」という言葉が出てきました。あんなに仕事が好きだった母がそう言ったことに驚きました。
当時、母は祖母を施設に入れるという選択肢を全く考えておらず、退院後は自宅で看るしかないと思っていました。そのため、「家で自分が看る=仕事を辞める」という結論に至ったようです。
しかし、病院のスタッフさんの協力のおかげで、施設入所という選択肢を知り、結果的に仕事を辞めずに済みました。入院後、祖母は有料老人ホームに入所し、叔父も同時に施設に入ることになり、ここから本格的な家族の介護が始まりました。
ダブルケアの毎日:子育ても介護も“そばにいるから”生まれる関わり
──お子さんの誕生とも時期が重なったのですね。
佐々木:はい。長男が生まれたのはちょうど5年前。そのころ父方の祖母も介護が必要になりました。メインのケアラーは父でしたが、僕も副介護者として3人のケアに関わることになりました。
──育児と介護が同時に来る“ダブルケア”の状況ですね。
佐々木:そうです。仕事と育児に追われながらも、施設に顔を出したり、祖母の外出に付き添ったりしました。
僕は主介護者ではありませんが、必要な場面で動ける存在として関わることが多かったです。大変ではありますが、「そばにいて支える」という感覚は子育ても介護も似ているなと感じました。
お金と制度の壁に向き合った叔父のケース
──叔父さんのケースでは金銭面の課題も大きかったそうですね。
佐々木:ええ。叔父の施設費用は祖母の貯金から賄っていましたが、やがて限界がきました。そんなとき母から「実家を売って費用に充てる」と聞かされ、本当に驚きました。
祖母が住んでいた実家に母も暮らしていたのですが、「2000万円くらいで売れるから介護費用に使う」と言い出して…。母自身の住まいについては「何とかなる」と言っていて、これはまずいと強く感じました。
叔父は当時60歳前後。まだ先が長い中で毎月の施設費用を払い続けるのは現実的に厳しかったんです。
僕には姉がいて、ここで役割を分担しました。生活保護の申請は僕が担当し、窓口で相談したり知人の税理士に助けてもらいました。姉は高額療養費制度を調べて、自己負担を減らす工夫をしてくれました。
結局、叔父は生活保護を受けられるようになり、施設費用の自己負担はなくなりました。周囲の人や制度に助けられたことは本当に大きかったと思います。
“副介護者”としてやってよかったと思えること
──副介護者として関わる中で、よかったと感じたことは?
佐々木:祖母の外出に付き添ったり、施設に顔を出した時間は負担というより思い出になりました。母にとっても、僕が橋渡し役になることで気持ちが少し軽くなったようです。
たとえば、施設から届く請求書は専門用語が多く分かりにくいことがあります。母が疑問を感じたときは、僕が施設に確認をして伝える。そんな通訳のような役割を担うことで、母と施設の関係も良好に保てました。副介護者だからこそ客観的に動けたのだと思います。
子どもと祖母をつなぐ時間が残してくれたもの
──介護を経験して、大切だと感じたことはありますか?
佐々木:子どもとの関係性はとても大事だと思いました。うちの息子は5歳ですが、月に一度は祖母たちに会わせていました。孫の成長を見守ることは、祖母たちや施設の職員さんにとっても励みになっていたと思います。
やっぱり、いつか人は旅立ちます。それがいつなのかは分かりません。でも「子どもがいる」という存在そのものが、祖母たちの生きる力になっていました。子どもと過ごす時間は、介護を超えて“家族の時間”そのものだったと思います。
僕自身も、自分が今ここで暮らせているのは祖父母や両親が必死に頑張ってきてくれたからだと実感します。だからこそ親や祖母を大事にしたいし、亡くなったあとに「会わせておいてよかった」と思えるんです。
人は「迷惑をかけたくない」と思いがちですが、元気なうちに「甘えること」も大事。祖母が亡くなったとき、子どもと一緒に過ごした時間を思い返して、本当にやってよかったと感じました。
編集後記:家族をつなぐ静かな役割
この記事では、副介護者という立場だからこそ築けた、家族間のあたたかなつながりについて教えていただきました。
特に、ケアが必要な祖母と幼い子どもが関わる時間は、双方にとって癒しと励ましの瞬間だったように感じます。
誰かを支える役割は、時に家族全体の関係性をやさしく変えていく力を持っているのだと、あらためて実感しました。
プロフィール
 佐々木 元勝(ささき・もとかつ)
佐々木 元勝(ささき・もとかつ)
36歳、理学療法士。元デイサービス管理者として10年以上介護現場に携わり、延べ3,000人以上の利用者と家族を支援。
母方・父方の祖母や叔父の介護に副介護者として関わり、仕事と子育てを両立する「ダブルケア」を経験。地域向けに介護や健康づくりのセミナーを50回以上開催し、介護や認知症を身近に感じてもらう活動を続けている。自身の体験をもとに電子書籍を2冊出版し、現場と家庭双方の視点から発信を行っている。
 執筆者:室津 瞳(むろつ・ひとみ)
執筆者:室津 瞳(むろつ・ひとみ)
NPO法人こだまの集い代表理事 / 株式会社チェンジウェーブグループ シニアプロフェッショナル / ダブルケアスペシャリスト / 杏林大学保健学部 老年実習指導教員
介護職・看護師として病院・福祉施設での実務経験を経て、令和元年に「NPO法人こだまの集い」を設立。自身の育児・介護・仕事が重なった約8年間のダブルケア経験をもとに、現場の声を社会に届けながら、働きながらケアと向き合える仕組みづくりを進めている。
【編著書】『育児と介護のダブルケア ― 事例からひもとく連携・支援の実際』(中央法規出版)【監修】『1000人の「そこが知りたい!」を集めました 共倒れしない介護』(オレンジページ)【共著】できるケアマネジャーになるために知っておきたい75のこと(メディカル・ケア・サービス)