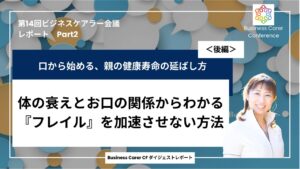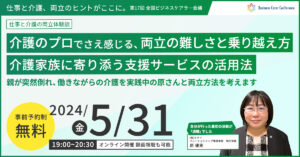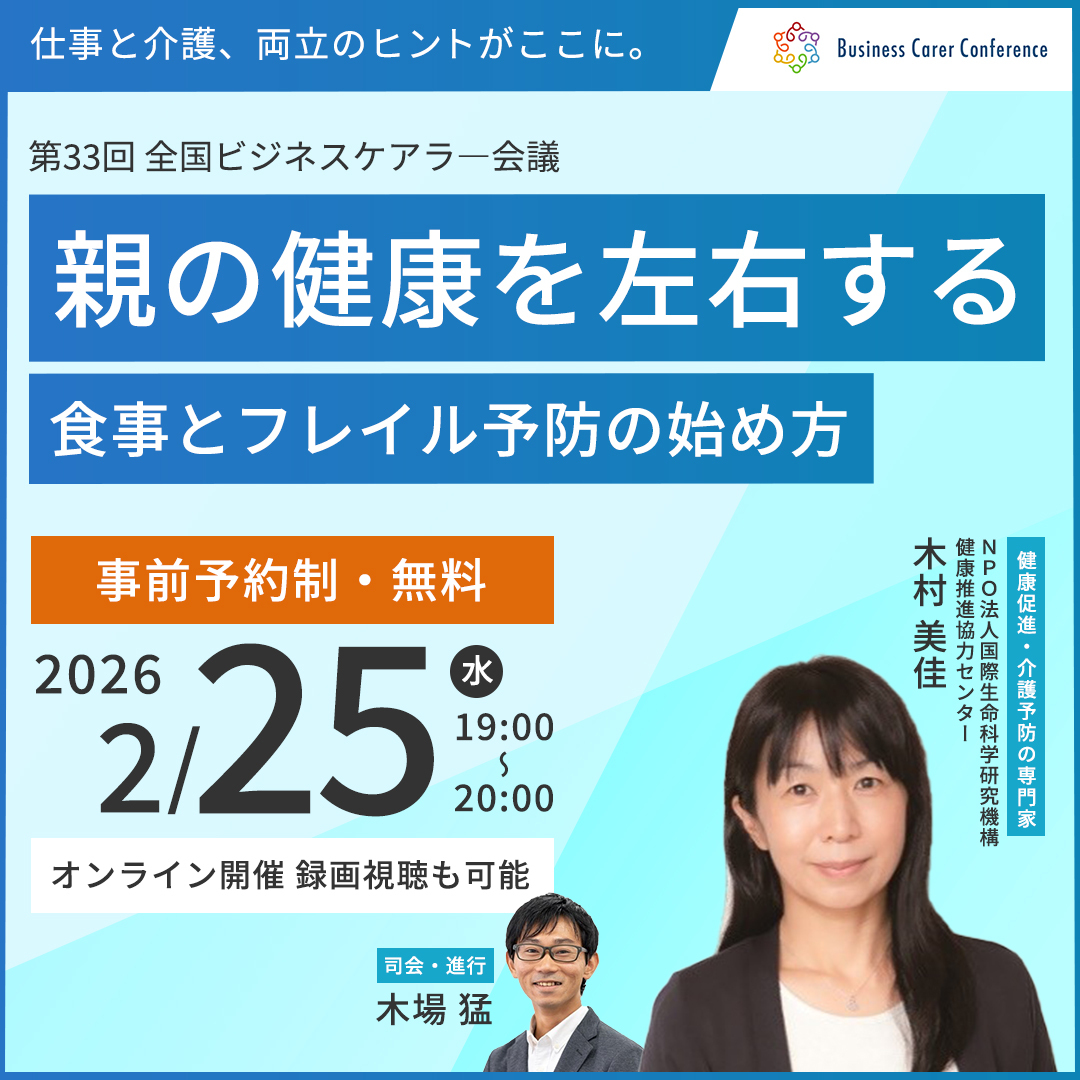「ダブルケア」時代の心と体を守る工夫

ダブルケアの本当のつらさとは?
育児と介護、どちらかだけでも日々の生活はめいっぱい。
それが重なる「ダブルケア」は、まさに時間・体力・感情の綱渡りです。
赤ちゃんの夜泣きと親の通院付き添いが同じ日に重なる、仕事の合間に保育園とデイサービスへの連絡……そんな日々が続くと、気づけば「息をつく暇がない」状態に陥ります。
そしてこのダブルケアのつらさは、単なる忙しさではなく、“責任と感情の板挟み”にあります。
自分のことを後回しにしながら、育てて、支えて、働いて──誰からも「がんばってるね」とは言われるけれど、本音は「もう限界かも」と感じている人も多いのではないでしょうか。
なぜこんなにしんどいのか
ダブルケアが過酷なのは、単純に“やることが多い”からではありません。
問題は、感情の質がまったく違う2つのケアが同時にやってくることです。
育児は「希望と未来」に向かうケア。一方、介護は「衰えと終わり」に向き合うケアです。そのため、心の負担が全然違う方向からやってくる。
さらに、相手の年齢もサポートの仕方も全く異なるので、頭の切り替えも一苦労です。
また、制度の壁もあります。育児支援は比較的整備されていますが、介護支援は「自分から情報を取りに行かないと使えない」仕組みが多く、知らないことで損をすることもあります。
人は、誰かを支えているとき、自分のエネルギーを削っていることに気づきにくいものです。
だからこそ、「なぜしんどいのか」を冷静に言語化することが、はじめの一歩になるのです。
支える人こそ、支えが必要
育児でも介護でも、「周りに頼れない」と感じる人は少なくありません。でも、すべてを自分でやろうとすると、どうしても無理が出てきます。
育児では保育園や一時保育、ファミサポなど、地域のサポートがあります。介護では地域包括支援センターやケアマネジャーが、状況に応じて制度やサービスを紹介してくれます。
重要なのは、「困ってから相談する」ではなく、「困る前に話をしておく」ことです。
また、職場にも「相談のハードルを下げる」努力が必要です。管理職や同僚との関係性が少し柔らかくなるだけで、「休みが取りやすくなった」「理解してもらえた」と感じる場面が増えるはずです。
自分だけで回さない。人と制度を組み合わせながら、「助けられる力」を持っていることも立派なスキルです。
「割り切り」と「つながり」が支えになる
完璧を目指そうとすると、どこかで必ず破綻してしまいます。
だからこそ大切なのは「割り切り」です。できないことはできないと割り切ること。やらない日があってもいい、レトルトやデリバリーの日が続いてもいい、書類が出せない日があってもいい。
また、誰かと「つながっている」感覚も大切です。近くに頼れる人がいなくても、SNSやオンラインコミュニティなど、同じような境遇の人とつながることで、「自分は一人じゃない」と思えることがあります。
ケアマネジャーの中には「がんばりすぎる人ほど、息抜きが難しい方が多い傾向がある」と語る方もいます。
忙しければ忙しいほど、自分の時間をとることには抵抗感が生まれがちですが、ご自身の心を守るためにも、意識的に“何もしない時間”を作ってみてください。こまめなティーブレイクをとる、ただ寝る、外を歩く。
小さなことが、心の余白を取り戻してくれるかもしれません。
自分を後回しにしないために
ダブルケアは、誰かのためにがんばる毎日であることが多いです。
でも、それを続けるには、「自分のメンテナンス」も同じくらい大事です。車だって、点検せずに走り続ければ壊れてしまう。人も同じですね。
「がんばりすぎない工夫」や「頼る勇気」は、弱さではなく知恵です。自分を大切にすることは、周りを大切にすることにもつながります。
人生のある一時期、育児と介護が重なる時期がある。
人によってその時間の長さに違いはあるけれど、濃密で、体にも心にも負担がかかりやすい時期です。
その期間を、どう過ごすか。あなたが倒れないことが、みんなにとっていちばん大事なこと。
だから、今日だけは、少し自分を甘やかしてみませんか?
この記事を書いた人
 室津 瞳(むろつ・ひとみ)
室津 瞳(むろつ・ひとみ)
NPO法人こだまの集い代表理事 / 株式会社チェンジウェーブグループ シニアプロフェッショナル / ダブルケアスペシャリスト / 杏林大学保健学部 老年実習指導教員
介護職・看護師として病院・福祉施設での実務経験を経て、令和元年に「NPO法人こだまの集い」を設立。自身の育児・介護・仕事が重なった約8年間のダブルケア経験をもとに、現場の声を社会に届けながら、働きながらケアと向き合える仕組みづくりを進めている。
【編著書】『育児と介護のダブルケア ― 事例からひもとく連携・支援の実際』(中央法規出版)【監修】『1000人の「そこが知りたい!」を集めました 共倒れしない介護』(オレンジページ)【共著】できるケアマネジャーになるために知っておきたい75のこと(メディカル・ケア・サービス)