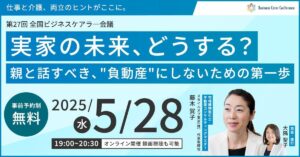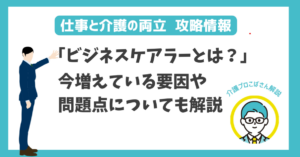1分でわかる「要介護認定の基礎知識」~仕組みと手続きの流れをやさしく解説〜
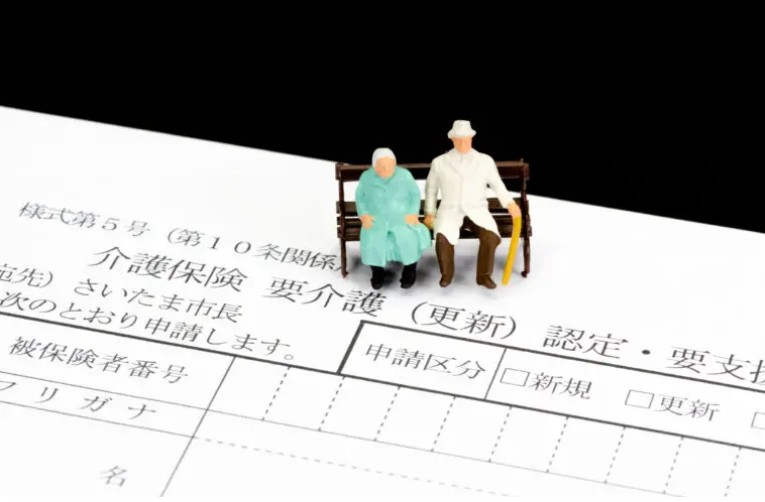
既に任意のご家族の介護をされている方も、そうなることを思い始めた方も、「要介護認定」は介護サービス利用の出発点となるだけに、まずは基本を抜けもれなく知っておきたいところです。
要介護認定とは
65歳以上の日本国民は全員、「介護保険被保険者証」を持っていますが、それだけで介護サービスを使えるわけではありません。
「日常生活に介護が必要かどうか」「どの程度の介護が必要か」を、一度はコンピューター判定を経て、その後に二次判定として、介護認定審査会が判定します。
判定結果は「非認定」「要支援1、要支援2」「要介護1〜5」の8区分に分けられます。サービスの使用可否や、使える範囲はこの区分によって大きく違います。
要介護認定の申請の流れ
1.申請
市区町村の窓口や地域包括支援センターに申請。家族や事業者による代行も可能です。
2.訪問調査
職員または委託調査員が自宅を訪問し、心身の状態を確認します。
3.一次判定
調査結果をもとに、コンピューターで一次判定が行われます。
4.二次判定
一次判定や主治医の意見をもとに、審査会が最終的な認定を決定します。
5.要介護認定の通知
一次判定や主治医の意見をもとに、審査会が最終的な認定を決定します。
要介護認定の評価基準
一次判定は心身の状況に関する基本調査をもとにコンピューターによって行われます。次の5項目を基に、どのくらいの介護時間が必要かという要介護認定等基準時間が算出されます。算出された時間と認知症加算の合計で判定が出る仕組みです。
1.直接生活介助(入浴・排せつ・食事の介護など)
2.間接生活介助(洗濯・掃除といった家事援助など)
3.問題行動関連行為(徘徊時の探索や不潔行為の対応など)
4.機能訓練関連行為(歩行訓練、日常生活動作訓練など)
5.医療関連(輸液の管理・褥そうの処置の診療補助など)
二次判定では、主治医の意見書と一次判定の結果をもとに、介護認定審査会が最終的な認定を行います。
イメージで理解する「要支援」と「要介護」の違い
要介護・要支援の区分により、介護保険で利用できるサービス内容や回数が異なります。たとえば要支援は、施設入所などの一部サービスは対象外となります。
| 自立 | 要支援 | 要介護 | |
| 区分 | 非該当 | 要支援1.2 | 要介護1~5 |
| 状態の違い | 日常生活は自立。 | 入浴、洗濯、掃除などの一部の支援が必要 | 自身で日常生活動作を行うことが難しく、常に介護が必要 |
表1 要支援と要介護の違い
要介護度別の判定基準と支給限度
基準時間によって「要支援1〜2」、「要介護1〜5」が判定されます。数字が大きいほど介護必要度が高く、月際の使用上限額も高くなります。
| 日常生活の状態 | 利用できるサービス | 要介護認定等基準時間(または相当すると認められる状態) | 支給限度基準額(月) | |
| 非該当 | 自立 | 介護予防・生活支援事業サービス | なし | 0円 |
| 要支援1 | 一部支援が必要 | 介護予防サービス | 25分以上32分未満 | 50,320円 |
| 要支援2 | 部分的な介助が必要(介護予防サービスにより機能の維持・改善が可能) | 32分以上50分未満 | 105,310円 | |
| 要介護1 | 部分的な介助が必要 | 介護サービス | 32分以上50分未満 | 167,650円 |
| 要介護2 | 軽度の介助が必要 | 50分以上70分未満 | 197,050円 | |
| 要介護3 | 中等度の介助が必要 | 70分以上90分未満 | 270,480円 | |
| 要介護4 | 重度の介助が必要 | 90分以上110分未満 | 309,380円 | |
| 要介護5 | 全面的に介助が必要 | 110分以上 | 362,170円 |
表2 要介護・要支援早わかり表
介護サービス利用までの流れ
希望するサービスを利用するためには、要介護認定を受けたあと、「ケアプランの作成」が必要です。要介護区分ごとにケアプラン作成の窓口が異なります。ケアプランに基づき、必要なサービスを開始します。
要介護【介護サービス】
- 在宅サービスを希望する場合は、居宅介護支援事業者のケアマネジャーが作成
- 施設入所を希望する場合は、施設のケアマネジャーが作成
要支援・非該当【介護予防サービス】【介護予防・生活支援事業サービス】
- どちらも主に地域包括支援センターがケアプランを作成
介護認定の有効期限と更新のポイント
要介護認定には有効期限があり、更新手続きをしないと全額自己負担になるため注意が必要です。申請は期限の60日前から可能で、早めの対応が望まれます。
初回は6ヶ月、以降は原則1年。有効期間は状態によって最長4年まで延長されることもありますが、進行性の病気などでは短縮される場合もあります。
更新時期を見逃さないために、介護保険課からの通知先を親元ではなく自分の自宅に変更しておくことも一つの方法です。
介護認定に抵抗感がある場合は
病気や退院をきっかけに、親の介護認定を検討する方は少なくありません。その際、親が認定調査を受けたがらない場合もあります。
こうしたときは、本人の気持ちに寄り添いながら「なぜ受けたくないのか」に耳を傾けることが大切です。一方的に勧めるのではなく、相手の立場に立って丁寧に説明し、「私が安心できるから」というIメッセージを使うことで、より穏やかに気持ちを伝えることができます。
おわりに
介護サービスを利用するには、すべて「要介護認定」から始まります。介護度の結果が出るまでには時間を要します。家族に支援が必要だと感じたときに、スムーズに介護サービスに移行できるように、前もって流れを把握しておくと安心です。
介護保険制度は一見複雑に見えますが、介護サービスの使い手はあなた自身です。もしわからないことや不安なことがあれば、その都度、遠慮せず専門職にどんどん聞いてみましょう。それが、納得して進めるための第一歩になります。