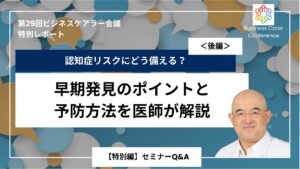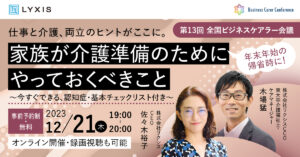母の介護に気づいたとき、自宅の暮らしをこう整えました ――仕事と子育てと重なる中での対応記録

【特別対談】田村あきこさん(仮名・東京都在住・大手金融機関中間管理職・ダブルケア歴8年) × ダブルケアスペシャリスト・室津瞳
中学生と高校生の2人の子どもを育てながら、要介護4・身体障がい1級の母親と暮らす田村あきこさん。
フルタイム勤務の傍ら、介護と育児を両立して8年。
“生活を整える”ことは、一度で完結するものではなく、何度も立て直しながら続いていくもの。
そのプロセスを、実体験に基づいて語っていただきました。
気づかず介護の状況
室津瞳(以下、室津):
最初にお母さまの介護が始まったときのことを教えてください。
田村あきこ(以下、田村):
最初は通院に付き添ったり、食事や洗濯を手伝ったりしていましたが、「介護している」という感覚はまったくありませんでした。ちょうど子どもたちの習いごとの送迎があったり、仕事も忙しくて……。母のサポートは、日常の延長のように思っていたんです。
寝たきりでやっと気づいた
室津:
介護者として自覚されたのは、どんなきっかけでしたか?
田村:
母がほぼベッド中心の生活になった4年前、かかりつけ医から「障がい者手帳の申請を考えてみては」と言われたんです。その瞬間、「あ、これはもう治る見込みがある状態じゃないんだ」とストンと腹落ちしました。制度を使う必要がある段階だと理解して、ようやく“これは介護だ”と自覚するようになりました。
最初に動いたこと:制度と環境の準備
室津:
そこから最初に動いたことは?
田村:
地域包括支援センターに電話をして、ケアマネジャーと面談しました。生活に必要な最低限の補助機器――介護用ベッドや電動便座などを導入しました。申請関係はすべて私が担当。当時は「これから始まるんだな」という気持ちと、「もう戻れないな」という重さが同時にありましたね。
お金のやりくりも体制の一部だった
室津:
費用面ではどのように対応されましたか?
田村:
母の年金だけでは医療費や介護用品の費用はとても賄えず、私が立て替える形が続いています。実家の不動産は動かせない事情がありましたし、限度額認定証や高額療養費制度などもフル活用して、やりくりしています。支出管理も、介護体制の一部だと感じています。
暮らしを「整える」ではなく「育てる」工夫
室津:
生活の中での工夫について教えてください。
田村:
スマートスピーカーやタブレットなど、手足の自由がききにくい母が“自分でできること”を増やせる環境を意識して整えてきました。音声操作も、最初は全然使えなかったんです。でも4年かけて少しずつ慣れて、今では自分でテレビをつけて、好きなドラマを観るまでになりました。
環境の導入だけでは意味がない。“どう動けるようになるか”を一緒に育てていく。まるで子どもの生活習慣を整えるような感覚でした。
気持ちを支える「その人らしさ」の演出
室津:
お母さまの気持ちの面では、どんなことを意識されていましたか?
田村:
母が好きなものを生活空間に“残す”ことを意識しています。たとえばリビングのテレビは、海外ドラマが毎日の楽しみなのでそのまま。昔よく弾いていたピアノも防音室に残しています。無理に何かをさせるのではなく、「やりたい」と思ったときにそれが手の届くところにある。そんな環境づくりを大切にしています。
外部サービスは“継続の仕組み”
室津:
介護サービスの利用についてはいかがですか?
田村:
訪問看護や介護タクシー、短時間の送迎なども積極的に使っています。最初は「自分でやらなきゃ」と思っていましたが、それでは続かないと気づいて。外の力を借りることは、介護を“持続可能にする仕組み”として必要不可欠です。
私が実際にやったこと(体制構築リスト)
室津:
ご自宅の中で実際に取り入れてきたことを教えてください。
田村:
はい、こんなことを進めてきました。
- 電動ベッド、電動便座
- 洗濯乾燥機、開けやすい冷蔵庫
- スマートスピーカー(音声操作)、タブレット
- 家具配置の見直し(母の動線確保)
- ケアマネジャー選定、訪問系サービス導入(訪問看護・介護タクシーなど)
- 各種申請(障がい者手帳、介護認定、限度額認定など)
- 通帳・印鑑の整理(代理手続き対応)
- テレビ・ピアノの設置維持(本人の楽しみを支える環境)
最後に
室津:
この記事をご覧になる方に、一言お願いします。
田村:
これはあくまで、私の例にすぎません。ご家庭によって状況は本当に違います。でも、「何から始めればいいかわからない」という時に、ひとつの参考になれたら嬉しいです。生活は、一度に整えるものではなく、何度も“作り直す”もの。そして、整えてから維持し続けられることが大切です。そんなつもりで、これからも向き合っていきたいと思っています。
編集後記
在宅介護の体制づくりは、「完成」ではなく「始まり」。田村さんの言葉からは、ひとつひとつ生活を組み直していくプロセスのリアルさと、その中で見えてきた“支える”とは何かがにじんでいました。制度や道具を揃えるだけで終わらない ――“動く暮らし”をつくる、その地道な努力こそが、介護を「暮らしの一部」に変えていくのかもしれません。
この記事を書いた専門家
NPO法人こだまの集い代表理事 / 株式会社チェンジウェーブグループ シニアプロフェッショナル / ダブルケアスペシャリスト / 杏林大学保健学部 老年実習指導教員
介護職・看護師として病院・福祉施設での実務経験を経て、令和元年に「NPO法人こだまの集い」を設立。自身の育児・介護・仕事が重なった約8年間のダブルケア経験をもとに、現場の声を社会に届けながら、働きながらケアと向き合える仕組みづくりを進めている。
【編著書】『育児と介護のダブルケア ― 事例からひもとく連携・支援の実際』(中央法規出版)【監修】『1000人の「そこが知りたい!」を集めました 共倒れしない介護』(オレンジページ)