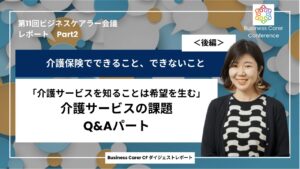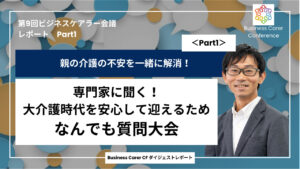夫と分担できない家庭で、私はどうした?~ダブルケア・ワンオペの乗り越え方~

【特別対談】田村あきこさん(仮名・東京都在住・大手金融機関中間管理職・ダブルケア歴8年) × ダブルケアスペシャリスト・室津瞳
首都圏でフルタイム勤務をしながら、高校生と中学生の2人の子どもを育て、要介護の母と一緒に暮らしている田村さん。
夫はずっと単身赴任で、いわゆる“ワンオペ”状態。でも、「なんとかやりくりしてきた」という彼女の話には、日々を回すためのリアルな知恵が詰まっています。
理想と現実:チームケアと言うけれど、分担できない家庭もある
室津 瞳(以下、室津):
田村さん、本日はありがとうございます。さっそくですが、ケアというと「家族で支え合って乗り切る」といった理想が語られることが多いですよね。
田村 あきこ(以下、田村):
そうですね。でも、うちの場合は「分担できない」のが前提なんです。夫は転勤族で、長男が生まれた時からずっと単身赴任。育児や介護に関われる状況ではありませんでした。
室津:
まさに“ワンオペ・ダブルケア”状態ですね。
田村:
はい。「夫と分担する」選択肢がない中で、どうすれば回せるか。そこにずっと向き合ってきました。
なぜワンオペになったのか:田村さんの家族構成と8年のダブルケア
室津:
家庭の構成について、あらためて教えてください。
田村:
今は高校1年と中学2年の息子がいて、実母と私の4人暮らしです。母は要介護4で身体障がい1級。リウマチで徐々に関節が動かなくなり、8年前から在宅介護が必要になりました。介護サービスとしては、車椅子や電動ベッドの貸与、訪問介護、通所リハビリを利用しています。
室津:
育児と介護が重なるタイミングはいつ頃でしたか?
田村:
長男を出産した15年前、保育園に入れず“保育園難民”になったんです。どうしても復職が必要だったので、関西で一人暮らしをしていた母に頼み、東京へ引っ越してきてもらいました。両親は離婚していて、母は動きやすい立場だったのも大きかったですね。
室津:
そこから「母+私」でまわしていく暮らしが始まったんですね。
田村:
はい。7年ほどは母と協力して子どもを育てていました。でも、その母がリウマチを発症して要介護に。そこからはもう、完全な“ワンオペ”になりました。
苦労は、“重なり”と“説明”の二重負担
室津:
ワンオペでのダブルケア、どんな点が特に大変でしたか?
田村:
一番は、「全部が重なること」。たとえば、子どもが体調を崩した日に母も具合が悪くなって、しかも仕事では大事な会議がある -そんな日が本当に多くて。
室津:
三者三様の優先順位がぶつかり合うわけですね。
田村:
はい。そのたびに「何を捨てるか」を瞬時に決める必要があるし、それぞれに理由を説明しなきゃいけない。母に、子に、職場に、学校に、ケアマネに。それぞれ伝え方も違うし、正直しんどいです。
室津:
ケアマネさんとのやりとりも工夫されていると伺いました。
田村:
以前、こちらの希望がうまく伝わらなくて、ヘルパーさんの訪問タイミングがすれ違ってしまったことがあったんです。その時に、「早めに来てほしい」だと伝わりにくいんだなと気づいて。今は「15時以降は介助が一切できません。その15分前までに訪問をお願いしたい」と、できないことを具体的に、時間もはっきりお伝えするようにしています。相手にとってもイメージしやすい伝え方が大事だなと感じています。
工夫は「誰を優先するか」を冷静に決めること
室津:
そうした複雑な状況の中で、日々どのようにバランスを取っているのでしょうか?
田村:
私の中で大事にしているのは、「誰が一番大事か」ではなく、「今この瞬間、誰を優先すべきか」で判断することです。
室津:
お母さまには、そのことを事前に伝えていたんですね?
田村:
はい。「もし母と子のことでハプニングが重なったら、子を優先するからね」と日頃から伝えています。ただ、実際そうなると母は怒ることもあります。そんな時は、一旦距離を取って、落ち着くのを待ちます。時間が経てば、だいたい冷静になりますので。
室津:
それでも罪悪感は残りますよね。
田村:
あります。でも、「全部をやろうとすると家族ごと共倒れになる」と、自分に言い聞かせています。ブレないように。「共倒れを避けるために優先順位をつけざるをえないこと」は冷静になった母にも繰り返し伝えるようにしています。
室津:
お子さんたちにはどんなふうに声をかけていますか?
田村:
中高生なので会話は少なめですが、何か問題があって落ち込んでいる時に、「私はいつでもあなたの味方だよ」と伝えるようにしています。本人が不安なときにこそ、言葉で支えるのが大事だと思っています。
室津:
状況に応じて優先順位を変えることも?
田村:
はい。たとえば母に血尿が出て、ちょうど子の面談と重なったときは、子に事情を説明して病院を優先しました。ベースの判断軸は持ちつつ、現実的に対応しています。
まとめ:ワンオペでも、“何を大切にするか”は選べる
室津:
ここまでのお話を伺って、ワンオペには限界もありますが、逆に自由度もあるように感じました。
田村:
そうですね。夫と分担できていればまた違った形があったかもしれませんが、誰かに確認したり話し合ったりする必要がない分、自分のペースで動きやすいというのは確かにあります。全部ひとりで判断できる分、生活は回しやすい部分もあります。
室津:
最後に、同じような悩みを抱える方に向けて、ひと言いただけますか?
田村:
夫と分担できなくても、「自分が何を大事にしたいか」を明確にしておけば、自分なりの軸で歩んでいける。そう思ってやってきました。
編集後記
「分担できないからダメ」ではなく、「分担できないなりの道を選ぶ」。
その視点こそが、これからのダブルケアに必要なマインドなのかもしれません。
田村さんの言葉が、同じように“ワンオペ”の日々を送るあなたの力になりますように。
この記事を書いた専門家
NPO法人こだまの集い代表理事 / 株式会社チェンジウェーブグループ シニアプロフェッショナル / ダブルケアスペシャリスト / 杏林大学保健学部 老年実習指導教員
介護職・看護師として病院・福祉施設での実務経験を経て、令和元年に「NPO法人こだまの集い」を設立。自身の育児・介護・仕事が重なった約8年間のダブルケア経験をもとに、現場の声を社会に届けながら、働きながらケアと向き合える仕組みづくりを進めている。
【編著書】『育児と介護のダブルケア ― 事例からひもとく連携・支援の実際』(中央法規出版)【監修】『1000人の「そこが知りたい!」を集めました 共倒れしない介護』(オレンジページ)