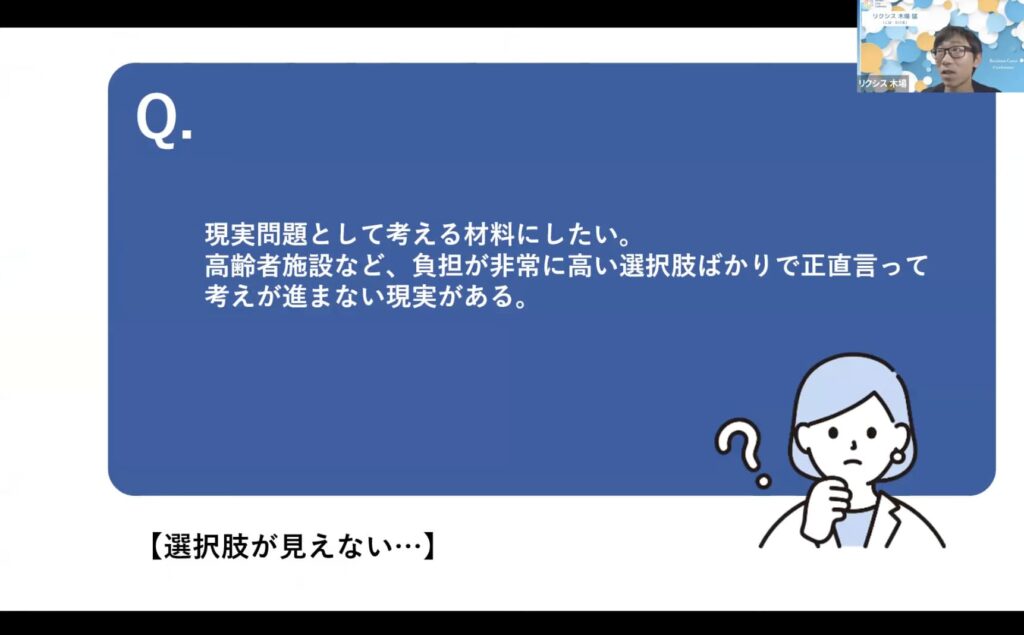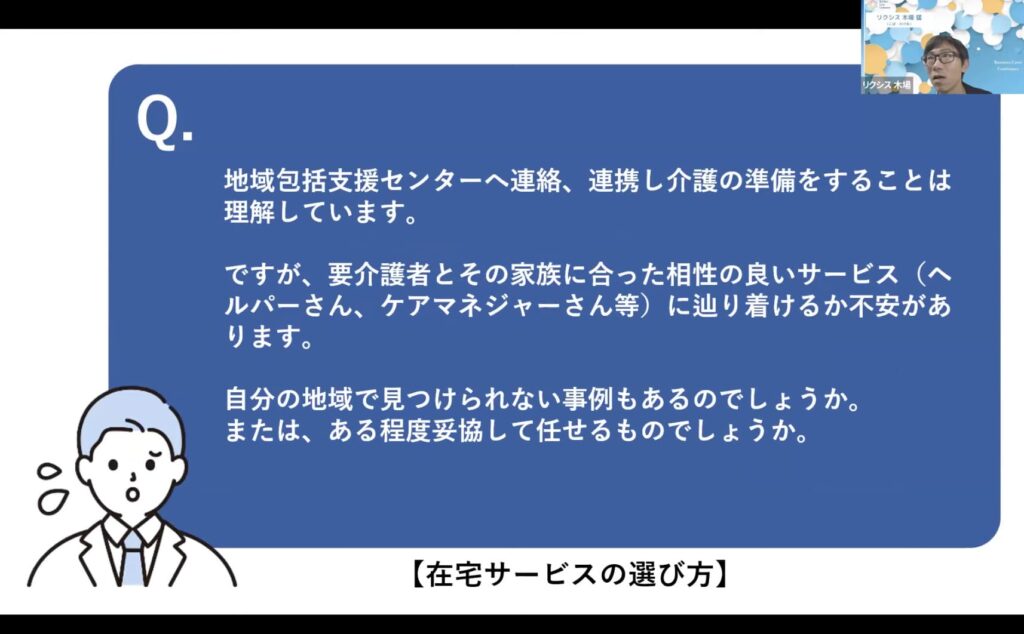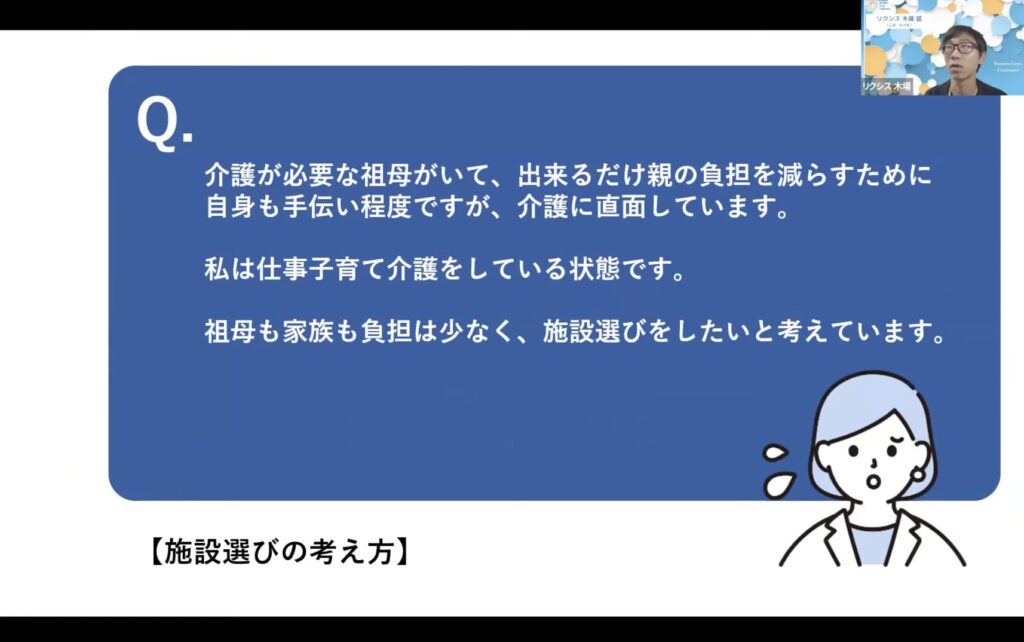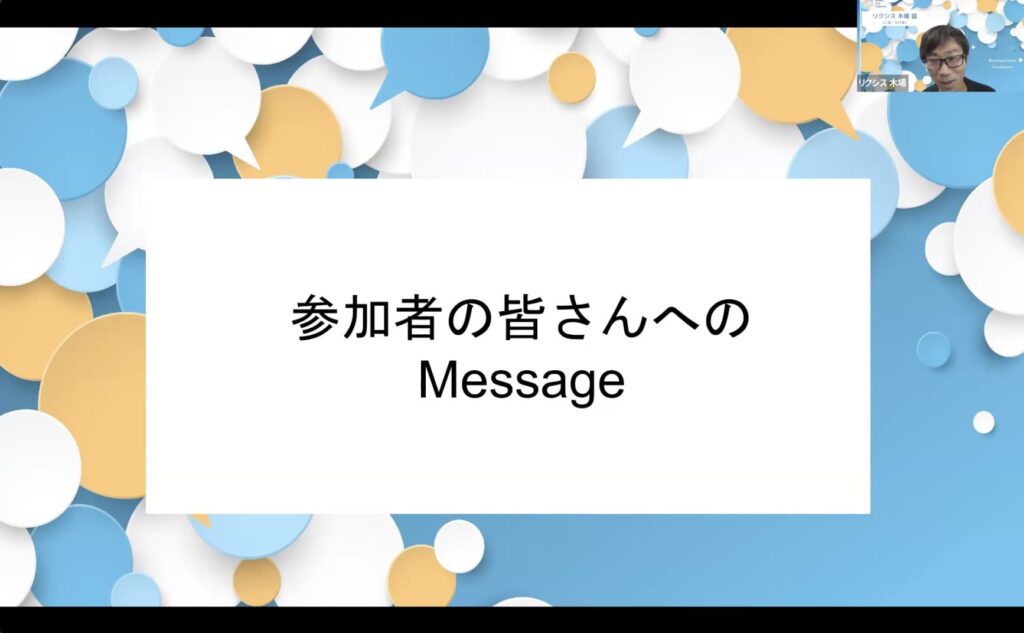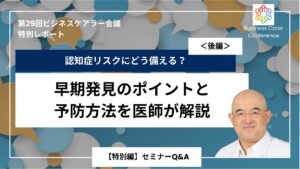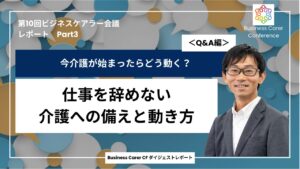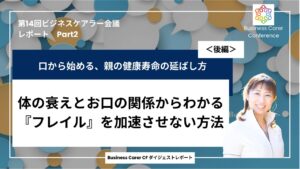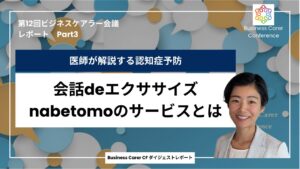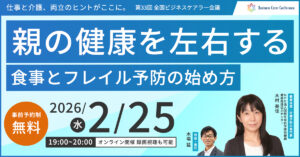介護費用?施設探し?遠距離介護?親の介護に振り回されない!今すぐできる、最初の一歩(後半)

ログインすることで、
ご視聴いただけます。
はじめに
2025年2月26日、リクシスは、第25回『全国ビジネスケアラー会議』を開催いたしました。
これから高齢社会がより一層加速し、仕事と介護の両立が当たり前の時代がやってきます。本オンラインセミナーは、高齢化の流れが加速する日本社会において、現役世代として働きつつ、同時にご家族の介護にも携わっている「ビジネスケアラー」の方々とその予備軍となる皆様に向けたセミナーです。
今回のテーマは「親の介護準備」。
介護は突然始まってしまうもの。高齢の親御さんがいるビジネスパーソンであれば、いざという時にどうすればいいのか気になっているという方も多いのではないでしょうか。
今回は、前半2,000世帯以上のご家族の「仕事と介護の両立支援」に携わってきたチェンジウェーブグループリクシス チーフケアオフィサーの木場氏が親の介護に関するアンケートをとりながら、後半には介護プロであるダブルケア支援の室津瞳氏、在宅介護と施設選びの専門家である有識者の高畑俊介氏をお招きし、皆さんの親の介護準備に対するリアルな質問に回答していただきます。
この記事では、
- 将来の介護に対して選択肢が見えずに不安な時は何をどう考えればいいのか
- 施設選びをどうしていけば良いのか
- 家族との介護でのすれ違いをどうしていけばいいのか
などのテーマでまとめています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①介護費用?施設探し?遠距離介護?親の介護に振り回されない!今すぐできる、最初の一歩(前半)
②介護費用?施設探し?遠距離介護?親の介護に振り回されない!今すぐできる、最初の一歩(後半)⇐このページのテーマ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
登壇者プロフィール
木場猛(こば・たける)
株式会社チェンジウェーブグループ リクシス(※2024年1月1日の経営統合により、社名が変更となりました)CCO(チーフケアオフィサー)
介護福祉士、介護支援専門員
ヘルパー歴22年以上 介護福祉士・ケアマネージャーとして延べ2,000組以上のご家族を担当。
東京大学文学部卒業。
高齢者支援や介護の現場に携わりながら、 仕事と介護の両立支援クラウド「LCAT」ラーニングコンテンツ作成や「仕事と介護の両立個別相談窓口」相談業務を担当。
3年間で400名以上のビジネスケアラーであるご家族の相談を受けた経験あり。
セミナー受講者数、延べ約2万人超。
【新書】「仕事は辞めない!働く×介護 両立の教科書」(日経クロスウーマン)
室津瞳(むろつ・ひとみ)
NPO法人こだまの集い代表理事
介護職・看護師として病院や施設勤務を経て、令和元年5月に「NPO法人こだまの集い」設立、代表理事に就任。自身も育児と介護と仕事の重なるダブルケアを約8年間経験する。
ミッションは「育児と介護が重なる現役世代が、 働き続けられる社会への実現〜多世代が活躍できる仕組みづくり〜」
【共著】「育児と介護のダブルケア-事例からひもとく連携・支援の実際-」(中央法規出版)
【監修】1000人の「そこが知りたい!」を集めました 仕事や育児と両立できる 共倒れしない介護 | オレンジページの本 | オレンジページnet
高畑俊介(たかはた・しゅんすけ)
ケアマネジャー
在宅介護と施設選びの専門家
施設介護・在宅介護の現場職員として10年以上勤務し、現在は在宅介護サービスをコーディネートするケアマネジャーとして活動。一方で、施設入居に関する相談も数多く受け、在宅と施設の選択に悩む方々を支援。また、SNSで介護に関する情報発信を続けるほか、介護サービス事業所のコンサルティングや介護関連メディアでの記事の校正・執筆を手掛ける。専門家として現場の視点を活かし、介護に関する正しい知識と実践的な情報を伝えることを大切にしている。
事前質問①介護についての選択肢が見えずに考えが進まない
質問内容
現実問題として考える材料にしたい。
高齢者施設など、負担が非常に高い選択肢ばかりで正直言って考えが進まない現実がある。
高畑氏:まずは、負担とは何の負担なのか、費用的なものなのか心理的なものかということについて、整理が必要かなと思います。施設だけではなく、在宅の介護サービスもたくさんあるということを知っていただきたいです。
例えば、ヘルパーさんやデイサービス、看護師さんが来てくれる訪問看護など、介護保険サービスには在宅で利用できるサービスがたくさんあります。そういったサービスを利用しながら施設の準備段階の時間を作るということもできます。
費用的な面でいうと、短期入所といって介護施設に短期間預かってもらうサービスもあります。そういったサービスを活用して入所施設への入所タイミングを遅らせることで、10年間ずっと施設という状況よりは、費用を削減することができるでしょう。
また、公的な補助制度を活用することで、費用的な負担を減らせるのではないかと思います。知っているだけで費用削減になる制度がたくさんありますので、専門家に聞いて負担感を減らしていくのが良いかなと思います。
先ほど介護にかかるお金の相場が10年間で約1,000万という話がでておりましたが、その金額だけ聞くと不安が募るかと思います。ですので、実際に自分たちが必要となる金額を明らかにすることが大事なのかなと思います。
木場氏:確かにインターネットなどで検索をすると、いきなり高い施設などが出てきてしまい不安になりますよね。
でも、実際はいきなり施設ではなくて在宅介護のサービスがあるよということを、まずは知っておくだけでも不安が少し減らせるかなと思います。
では、ヘルパーさんを利用したいという場合にはどうすれば良いでしょうか?
高畑氏:まずは介護度を認定してもらい、ヘルパーさんを利用する必要があるのかを専門家の方に決めていただかなければなりません。そのためにも、最初は地域包括支援センターにご相談ください。
事前質問②在宅サービスの選び方がわからず自分の地域で見つけられるか不安
質問内容
要介護者とその家族に合った相性の良いサービス(ヘルパーさん、ケアマネジャーさん等)に辿り着けるか不安があります。
自分の地域で見つけられない事例もあるのでしょうか。
または、ある程度妥協して任せるものでしょうか。
高畑氏:ケアマネジャーさんは在宅介護サービスをコーディネートする立場なので、1番根幹になる方です。良い人悪い人ということではなく、相性というものがありますので、合わないと思ったらいつでも変更することができるということを知っておいてください。
ヘルパーさんにおいても変更は可能かと思います。事業所の方に相談してみるのが良いでしょう。
事業所の雰囲気やスタッフの方々の対応が合うか合わないかというのは、実際に利用してみないと見えてこないことも多いです。口コミなどはどうしても主観的な意見になってしまうので、一度体験していただくのが1 番良いかと思います。
デイサービスなどでは体験がありますし、施設の場合はショートステイをしていただくということになります。
木場氏:地域包括支援センターに相談して要介護認定を受けると、ケアマネジャーの方が窓口になってご家族の相談を受けて介護サービスを手配したり調整したりします。
このケアマネジャーさんはいつでも変更できるということをお伝えいただきました。
ただ、地域によっては、ヘルパーさんが不足しているところもあると聞きます。なかなか変更できず、合う方を見つけられないという時はどうすればいいでしょうか?
高畑氏:確かにヘルパーさんの不足というのは全国的に話題になっていますので、ある程度この事業所のヘルパーさんはこの地域には行けないといったことが、これからどんどん増えてくる可能性があります。
もしそういったヘルパーさんの人数に限りのある地域にお住まいの場合には、今利用しているヘルパーさんに対して「こういった対応をお願いします」ということを忍耐強く伝え続けていただけたら良いかなと思います。
木場氏:確かにそうですね。私はもともとヘルパーをしていたので分かりますが、初めて行くお家のことですので、ご家族から色々お聞きできた方がありがたいなと思います。
事前質問③施設選びをしていきたいけどどのように考えればいいのか
質問内容
介護が必要な祖母がいて、出来るだけ親の負担を減らすために自身も手伝い程度ですが、介護に直面しています。
私は仕事・子育て・介護をしている状態です。
祖母も家族も負担が少ない施設選びをしたいと考えています。
高畑氏:とても意識の高いお孫さんだとお見受けしました。
実際に介護をメインで行っている方は、自分がどれだけ疲弊しているのかわからないということがよくあります。
なので、この方のように客観的に見る立場の方がいるととても良いですね。ケアマネジャーさんやサービス事業者さんに、ご家族が疲れているということを伝えておくと良いでしょう。その上で、施設選びについて一緒に情報収集をして選んでいくのが良いかと思います。
その時に「何を基準に選ぶか」という優先順位をケアマネジャーさんにお伝えしてください。例えば、頻繁に面会に行きたいから立地を優先するとか、提供されているサービス内容で比較するとか、客観的な立場にあるからこそご本人やご家族から聞き出しやすいということもあると思いますので、ぜひ確認して一緒に選んでみると良いでしょう。
木場氏:この方はダブルケアラーでもあるのですが、ダブルケアラーとしての負担の軽減方法について何かアドバイスはありますでしょうか?
室津氏:ダブルケアというのは、狭い意味では育児と介護が重なっている状態のことを言いますが、広い意味では親族内に複数の人のケアが必要な状態のことも言います。
この方は大変な状況にいらっしゃるかと思うのですが、お子様を優先しても良いということをまずはお伝えしたいです。
マルチタスクの状況で何が1番大切かを選ぶのは難しいでしょう。ただ、私の経験上はお子様に目を向けて良いと思っています。介護が物理的に忙しくなると、育児になかなか目を向けられないというジレンマが生じます。子どもも大事にしたいけれど目を向けられない。そうすると、子どもの心が閉じていったり、登校渋りが起きてしまったり、いろんな反応を示す場合があります。
私の場合も、当時娘が3歳だったのですが、ダブルケアしている時期っていうのは覚えていて我慢していたようです。やっと10歳になって言ってくれるようになりました。
もし、なかなかそうはできないという時には、先程のお話で「もしおばあちゃんが元気だったら何て言うかな?」というのを考えてみると良いでしょう。
木場氏:確かに、お孫さんを放っておいて面倒みてほしいというおばあさんは、おそらくそんなにいないだろうと思いますからね。
事前質問④当事者としての意識が薄い夫とのコミュニケーションをどうすればいいか
質問内容
義両親のことなのに、当事者意識が低くて動かない夫。
自分ごととして、捉えられるきっかけなどをどう作るかを知りたいです。
室津氏:すごく難しい話ですよね。夫が家事の部分には介入しづらいというお話を聞くことも確かに多いです。
私が聞いている話ですと、介護とか家事は手が出せないパートナーさんが多いようですが、お子さんのケアだと介入がしやすいというパートナーさんも傾向としていらっしゃるようです。どの部分だったらやってくれるだろうということを考えてみると良いかもしれません。
あとは、少し「おだて論」ということになってしまい申し訳ないのですが、第三者に褒めてもらうと頑張る気持ちになるパートナーさんもいらっしゃるようです。
すみません、回答になっているかわからないのですが、もしよろしければ試してみてください。
木場氏:義理のご両親ということで、パートナーから見たら自分の親のことなのに動こうとしない方のことを、何かやるということが決まっているタイミングではない時に動かすのは、かなり大変なことですよね。
まずは、このビジネスケアラー会議を見せてあげてください。
事前質問⑤介護の分担において「嫁」に負担が偏ってしまう
質問内容
介護の分担において、近くにいる者の負担が大きい。
役割分担を難しく考えている。どのようにしたらいいか。
また、親族に女性がいない場合、嫁という立場で、当たり前に仕事を両立しながら、病院の付き添い等をやっている。
話し合いをしても改善しない。今後不安が募る。
室津氏:お嫁さんの規範というのが地方だとより色濃く残っていることもありますので、難しい課題ですよね。
病院付き添いなどを行っているということですので、介護のプロの介入を導入してみて第三者からちょっと話してもらうというのが良いかもしれません。
身内でも、どの方であればこの話を聞いてくれそうか、パートナーさんや義理のご両親など可能なところからコミュニケーションをとっていくというのはどうでしょうか。
木場氏:身内に1人でも味方がいないと辛いだろうなと思って聞いておりました。パートナーの方がお話を聞いてくれる方だと良いですよね。
室津氏:そうですね。すごくパートナーシップが大切になってくることかと思います。
マネジメントが得意な方は、月に1回は子どもを抜きにして必ず夫婦の話し合いの時間を作るようにしていると言っていました。
定期ミーティングのように育児や介護の話をしていくことで、そこからマネジメントが始まるかなと思います。
当日質問:初めて地域包括支援センターに相談するときに何を準備しておいた方が良いか
質問内容
初めて地域包括支援センターに相談するとき、準備しておいた方が良いことは何でしょうか?
母の物忘れが多くなってきていて、初めて自分で「どうしようね」と伝えてきました。
早めに相談した方がいいとおっしゃっていたので連絡したいと思っています。どのようなことを聞かれるのか、初めての相談に伝えるための準備などあったら教えてください。
高畑氏:まずは来てもらうことが一番大事なのですが、相談の中で事前情報として必要な普段の状況を伝えてもらいたいと思います。
物忘れとはいうものが一般的に「物忘れ」と言われるものなのか、病的な認知機能の低下なのかを、専門職の方は線引きしようとします。その際に具体的なエピソードを出していただくといいのかなと思います。
そのための準備として、「こういう言動があったよね」とか「こういう物忘れをしていたよね」ということを、家族で話し合ってください。そこで出てきた情報をメモしておくとか、日記につけておくとか、そういったことが非常に有効になってきます。
木場氏:「自分はここまでが限界です」というような、自分の事情を最初から言っておくと良いと思います。
「たまたま今回一緒に来ましたけど普段来られません」など、言われないと担当者もわからないことがあって、それで動きが変わることもありますので。
参加者の皆さんへのメッセージ
室津氏:まずはご自身の健康を1番大事にしていただけたらと思います。ゆとりがないと育児も介護も仕事もできません。ゆとりがもてるようにやっていただきたいです。
また、ダブルケアラーの方は、子どもに目を向けて全然大丈夫ですよということをお伝えして、最後のメッセージに代えさせていただきます。ありがとうございました。
高畑氏:家族介護というのは、プレイヤーにならずマネジメント側に回っていただくのが1番いいかなと思います。実際の介護のことはプロに任せて、ご本人さんの思いとか生活歴とか、こういう人生を歩んできたのだというところをしっかり伝えていくというのが、ご家族の役割であると思いますので。
そういったことを伝えて、どんどんプロの方にお任せしていくっていうのを、ちょっと心に留めていただきたいです。ありがとうございました。