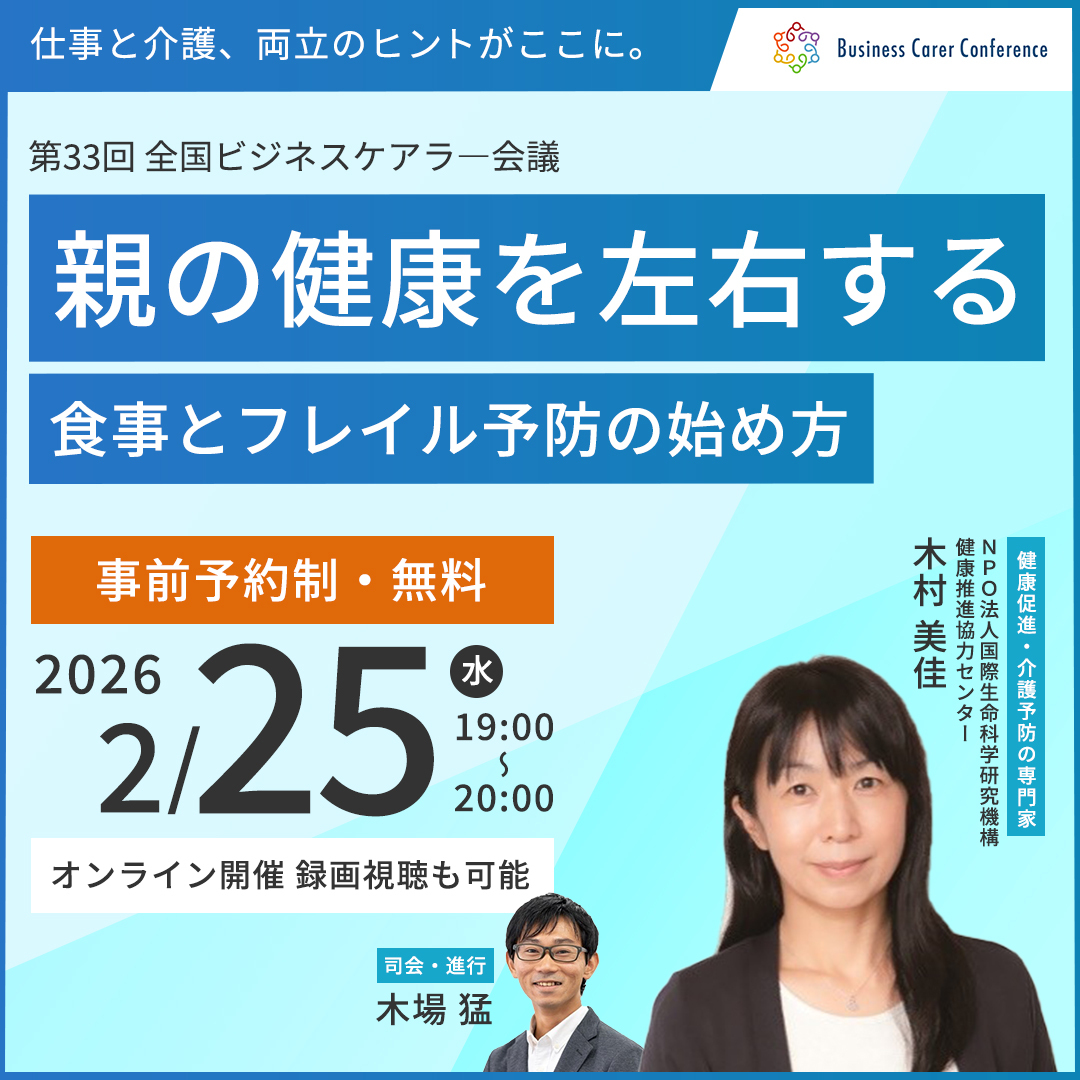1分でわかる「リモート介護ツール」(後編)~そばにいなくても支えられる“人の手”と“ちょっとした工夫”
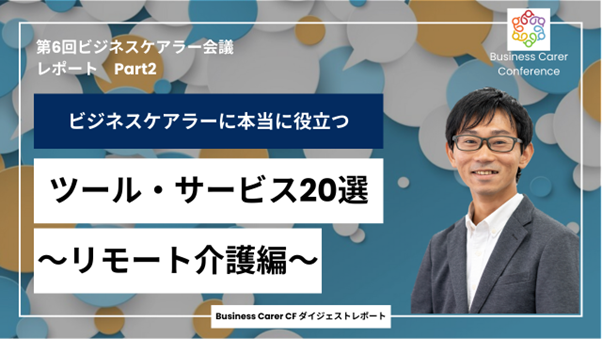
「見守りのIT機器は気になっているけれど、実際に親の生活で困っているのは“ちょっとしたこと”なんだよな…」
そんな声を聞くことは少なくありません。
日々の家事や買い物、話し相手や簡単な頼まれごと。ヘルパーさんを呼ぶほどではないけれど、誰かの手があるだけでグッと楽になることも多いものです。
今回は、介護の現場を20年以上見てきたプロ・木場猛さんが選んだ、「リモート介護を支える生活サポートツール・サービス」をご紹介します。
頼れる人を呼ぶ──家事代行・人材マッチングサービス
「ちょっと見ていてほしい」「電球を替えてほしい」「買い物の付き添いをお願いしたい」
そんなときに柔軟に使えるのが、家事代行や人材マッチングサービスです。
たとえば、「東京かあさん」は、家庭的なサポートが特徴で、料理や掃除、話し相手など幅広く対応。「もっとメイト」は若い世代のスタッフが高齢者の生活を楽しくサポートするのが特徴です。
ユニークなものでは、「レンタルおじさん」というサービスも。1時間1,000円という価格設定で、特別な作業をしなくても「ただそばにいる」存在が求められる場面で活用されています。
また、資格を持ったヘルパーによる「自費ヘルパーサービス」も選択肢のひとつです。介護保険では対応できない内容(掃除や外出支援など)も相談でき、気に入ったヘルパーを指名することも可能です。
日々の暮らしを支える移動・買い物・金銭管理サービス
高齢になると、買い物や外出などの移動が一気にハードルになります。最近では、こうした「日常の困りごと」を遠隔でフォローできるサービスが増えてきました。
ネット通販の【Amazon】【楽天】などは、定期配送や家族からの代理注文に対応しており、受け取りもヘルパーが代行することで使いやすくなります。
地域によっては、【生協】や【ヨシケイ】などのミールキットもまだ紙の注文が可能。ご本人が自分で選べる喜びを残しつつ、調理の負担を軽くする手段になります。
また、配食サービスの中には、体調や疾患に合わせたメニュー調整に対応してくれるものもあります。お弁当の受け取り時に「声かけ」や「安否確認」をしてくれる事業者もあり、実質的な見守りとして活用するケースもあるようです。
金銭管理が心配なご家庭では、使いすぎを防ぐプリペイドカードや、使用履歴が確認できるキャッシュレスサービスも登場しています。使う人が安心して買い物できる仕組みを用意することで、家族にも本人にもメリットがあります。
孤独や無気力に寄り添う、ロボットと便利グッズの力
「やることがない」「誰とも話していない」──
介護を必要とする前の段階から、こうした声はよく聞かれます。そんなときに役立つのが、コミュニケーションロボットや、日常の不便を和らげるグッズです。
【LOVOT(ラボット)】は、ぬくもりを感じる動きが特徴の“喋らないロボット”。介護施設で導入された際も、普段あまり動かない方が自ら手を伸ばしたというエピソードがあるそうです。赤ちゃんのような存在が、自立心や笑顔を引き出すこともあります。
【ROBOHON】や【BOCCO emo】は会話機能があり、見守りや音声メッセージ送信機能も搭載。見守りの延長として、やさしく生活に溶け込む存在になります。
さらに、「複雑なリモコンが使いづらい」といった声には【汎用テレビリモコン】、「来客があっても気づけない」なら【光るチャイム】、「鍵の管理が不安」な方には【キーボックス】など、少しの工夫で日々の安心が増える道具も豊富です。
まずは公的支援から。必要に応じて民間サービスをプラス
ここまで、さまざまな「リモート介護で使える民間サービスやツール」をご紹介してきましたが、木場さんが最後に強調したのは「まずは介護保険サービスを使うこと」の大切さでした。
介護保険を使えば、認定後は自己負担1割でヘルパーが来てくれることもあります。例えば1時間あたり300〜400円程度で受けられるサービスも多く、経済的にも安心です。
民間のサポートは、こうした公的サービスでカバーしきれない部分を補うものとして、無理のない範囲で組み合わせていくのが理想です。
まとめ:自分たちに合った方法で、無理なく介護を続けていくために
リモート介護の活用方法は、ご家族の状況や親御さんの性格、介護の段階によって本当にさまざまです。介護の不安に向き合うとき、すべてを自分でやろうとする必要はありません。
「自分では難しいことを、人やツールに頼ってもいい」。
そう思えるだけで、少し気持ちが楽になることもあります。
仕事と介護を両立するために。介護負担を少しでも軽くするために。そして何より、大切な人が安心して暮らし続けるために。ツールやサービスを上手に取り入れていくことで、それぞれのご家庭に合った“無理のない支え方”がきっと見つかります。
今回ご紹介した内容が、これからの選択肢を広げるヒントとなり、少しでも皆さまの安心につながれば幸いです。