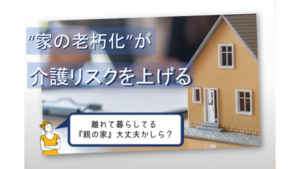ペットロスを乗り越える、心の整理のしかた

「わかっていても寂しい」のは自然なこと
「いつかこの子とも別れが来ることは、わかっていた」——そう思っていたはずなのに、いざその時が来ると、胸にぽっかりと穴があいたような感覚に包まれます。
朝、目が覚めたとき。いつものように家に帰ったとき。ふとした瞬間に、そこにいたはずの存在がいないことに気づく。
そのとき胸に押し寄せる寂しさは、言葉にならないほどの重さをもっています。
ペットロスは、ただの喪失ではありません。大切な家族との別れです。
多くの人にとって、ペットは子どものようでもあり、きょうだいのようでもあり、時には親友のような存在だったことでしょう。
だからこそ、その別れは深く、心の奥まで響くのです。
この記事では、ペットロスとどう向き合っていくか、そして支援する立場としてどんな寄り添い方ができるのか。
その一つの在り方を、丁寧に紐解いていきます。
ペットロスを乗り越えた先にあるもの
ペットとの別れは、老いのプロセスのなかにある自然な喪失体験のひとつです。人は年を重ねる中で、徐々にさまざまな「手放し」を経験していきます。体力や役割、職場でのポジション、そして家族との関係性。そうした変化のなかで、ペットが与えてくれる「無条件の愛」は、人生の心の支えとなっていることも多いものです。
だからこそ、その存在を失うとき、私たちは一時的に心のバランスを崩します。日々の生活が色あせて感じられ、食事や睡眠にも影響が出ることさえあります。
けれど、年齢を重ねた人が持つようになるのは、こうした喪失さえも自分の糧に変えていける力です。
それは、過去の経験を通して少しずつ培われた、人生に静かに向き合う強さでもあります。
ペットロスは必ずしも「克服すべき課題」ではありません。むしろ、「これまでの自分の歩みや経験を生かして、どう付き合っていくか」を考えることで、その体験は人生をしなやかに歩むための力になる可能性を秘めています。
視点を変えることでできること
心の痛みをやわらげるためには、「いなくなった事実」に意味を与えることがひとつの手がかりになります。
たとえば、こんなふうに考えてみることもできます。
- 「あの子は、自分に何かあったときに迷惑をかけないよう、先に旅立ったのかもしれない」
- 「もしも私が先に旅立ったら、あの子はとても寂しがったと思う。この寂しさは、あの子のためにわたしが引き受けてほぐしていこう」
- 「またいつか、天国で会える。その日を楽しみにして、生きていこう」
- 「たくさんの幸せをくれた分、今度は自分が誰かを支える番だ」
こうした“意味づけ”は、無理にする必要はありません。また、その人自身が意味づけるもので、周りが諭すものでもありません。
でも、少しずつでも視点を変えていくことで、心がほんの少し軽くなることがあります。そして、自分の気持ちを否定せずに受け止めることが、ペットロスとの向き合いの第一歩です。
支援者としてできること
もし身近にペットを亡くしてつらそうにしている人がいたら、支援する側にできることは何でしょうか。
以下に、支援者としてできる具体的なかかわり方のヒントをご紹介します。
①「悲しんでいいんだよ」と伝える
まずは、その人が感じている寂しさや涙を否定せずにまるごと受け止めることから始めましょう。
「今はそういう時期なんだと思います」「泣いてもいいですよ」「悲しむ自分を受け止めてあげてください」——そんなひと言が、その人を少し安心させ、心の不安を吐き出すきっかけになります。悲嘆を否定しないことは、悲嘆を浄化させる第一の過程として、とても大切です。
②日常のリズムを大切にできるよう見守る
特別な何かをしなくても、食べる・寝る・起きる・働くという日々のリズムを続けるだけでも十分です。忙しく過ごしているうちに、ふと心が軽くなる瞬間がやってくることもあります。
「ちゃんとごはん食べてる?」「今日は少し散歩してみませんか?」など、無理のない声かけが支えになります。
③問いかけで、そっと思い出を引き出す
- 「今、○○(ペットの名前)がいなくなったことには、どんな意味があると感じていますか?」
- 「○○は、どんな存在でしたか?」
- 「○○から学んだことや、もらったものって、どんなことがありますか?」
こうした問いかけは、その人自身が、自分の気持ちと向き合い、言葉にして整理するためのきっかけになります。ただし、無理に問いかける必要はありません。相手が自ら思い出を語り出したときや、気持ちを誰かに伝えたい様子がうかがえるときなど、心が少し落ち着いている場面でそっと訊ねてみてください。
④“抱きしめられる存在”の提案をする
ぬいぐるみや、毛の手ざわりに近いクッション、ペット型ロボットなど、「命」ではなくてもそばにいるように感じられる存在が支えになることもあります。最初は抵抗があるかもしれませんが、「この子は、○○の代わりじゃないけど、そばにいてくれる存在」と思えるようになることもあります。
いまは、さまざまなタイプのコミュニケーションロボットが登場しています。ただ可愛いだけではなく、どんな関わり方を求めているかによって、選ぶべきロボットも変わってきます。
たとえば、
- 肌触りを重視したいなら:柔らかい布製や動物のようなぬくもりを持ったもの
- 見た目の可愛さを重視したいなら:ペットのようなフォルムや愛嬌のある表情のあるもの
- 会話を楽しみたいなら:簡単な雑談や声かけに応じてくれる会話型ロボット
といったように、それぞれの癒され方のスタイルに応じたロボットを選ぶと、より心の支えになりやすくなります。
無理にすすめるのではなく、「こういうのもあるみたい」と軽く紹介して、選ぶ楽しみを持ってもらうことも大切です。コミュニケーションロボットのおすすめは、こちらのページからもご参照いただけます。
▼保険外サービス紹介:高齢者の孤独解消(コミュニケーションロボット・話し相手)
⑤時間がかかっても心の回復を信じて待つ
自分の関わりが何も役に立たないと思うこともあるかもしれません。でも、何かを「してあげる」ことよりも、そばにいて、待つことこそが大きな支援になります。
悲しみは人によって深さも長さも違います。その人の中に温かさが戻るには時間がかかるものです。無理に励ましたり、「もう元気出して」と言ったりせず、その人が自分のペースで癒えていくのを見守ること。急かさず、焦らず、何年かかってもいいと心得て、静かにそばにいることが何よりの支援です。
まとめ:前を向くための小さな一歩
ペットとの別れは、誰にとっても深い痛みをともなう体験です。
でもそれは、「忘れなければいけないもの」でも、「乗り越えなければいけない課題」でもありません。
悲しみを抱えたまま、日常を生きていくこと——その中で、ほんの少しずつ心の中にあたたかさが戻ってきます。
時間はかかっても大丈夫。悲しみの中であっても、人はやさしさを育てていく力を持っています。最初はただつらくて苦しいだけだった喪失も、あるときふと、「あの子と過ごせてよかったな」と思える瞬間に変わっていくはずです。
そのとき初めて、あなたは、別れが“終わり”ではなく、“つながり直し”の始まりだったことに気づくことでしょう。
この記事を書いた人
 岩瀬 良子(いわせ・りょうこ)
岩瀬 良子(いわせ・りょうこ)
介護支援専門員(ケアマネジャー)/介護福祉士
京都大学卒業。病院・施設・在宅など多様な現場に従事し、英国ホスピス視察などを経て「地域ケア」と「納得のいく看取り」を探求・実践する。
現在はその知見を活かし、「仕事と介護の両立」に関する個別相談やQ&A対応、専門記事の編集を担当。現場のリアリティと専門知識に基づいた、正確で温かみのある情報発信を行っている。
【執筆協力】中央法規出版『生活援助従事者研修 公式テキスト』








と、それへの代表的な批判について-300x169.png)