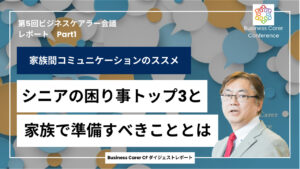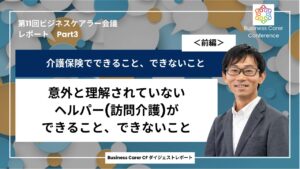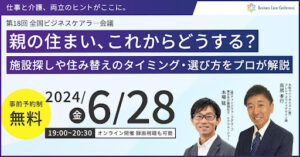1分でわかる「働く世代のキャリア形成と親の介護」
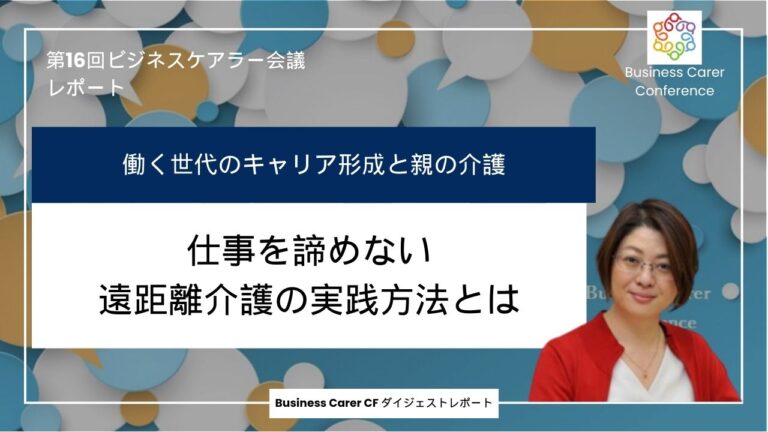
キャリアの充実期に差し掛かった40〜50代。昇進や新しい挑戦を控えながらも、親の介護が突然始まる可能性は誰にでもあります。「今はまだ大丈夫」と思っていても、ある日訪れる変化が、人生設計を揺らすことも珍しくありません。
この記事では、働く世代がキャリアを諦めずに親の介護と向き合うための視点を整理します。第16回『全国ビジネスケアラー会議』(2024年4月25日)より。
ビジネスケアラーという新しい現実
仕事と介護を同時に担う人を「ビジネスケアラー」と呼びます。共働きが一般的となった今、親の介護を家族の誰かだけに任せるのは難しくなりました。
経産省の試算では、2030年にはビジネスケアラーによる経済損失が約9兆円にのぼるとも言われています。つまりこれは、個人だけでなく社会全体の課題でもあります。
キャリアと介護のはざまで起こること
介護は、生活に突然割り込んできます。しかも、日常の延長線上にある“ちょっとした変化”から始まることが多いのです。
親が外出を控えるようになった、階段を手すりなしで昇らなくなった、同じ話を何度も繰り返す…。離れて暮らしている場合、こうしたサインを見逃してしまいがちです。
気づいたときには、介護の体制を整える必要が一気にやってきます。その中で直面しやすいのが、次の4つの課題です。
- 時間の制約:仕事と並行して、介護の準備・調整を行う必要がある
- 心身の負担:仕事と介護のペースの違いによる疲労やストレス
- 経済的な負担:教育費や住宅ローンに加わる介護費用
- キャリアの中断リスク:昇進やプロジェクト参画の機会が減る
「3Gギャップ」が示す時代の変化
ビジネスケアラーの背景には、3つのギャップがあります。
まず、ジェンダーギャップ。男女ともに働く時代となり、誰が介護を担うかが不明確になっています。
次に、ジェネレーションギャップ。親世代の「介護は家庭で」という価値観と、現役世代の現実的な感覚のずれです。
そして、ジオグラフィカルギャップ。核家族化や転勤などで、物理的な距離が離れて暮らすケースが増えています。
キャリアを諦めないためにできること
介護が始まる前に、「自分だけで抱え込まない仕組み」を知っておくことが大切です。
地域包括支援センターやケアマネジャーなど、行政や専門職を早い段階から頼ることは、決して弱さではなく、両立のための戦略です。
また、職場とも情報を共有しておきましょう。介護休暇や時短勤務などの制度は、知っているかどうかで選択肢が大きく変わります。キャリアの継続と親の生活の安心を両立させるには、仕事と介護の体制を同時に設計する視点が欠かせません。
今からできる小さな備え
- 親の生活習慣や健康状態を定期的に確認する
- 家族間で介護時の役割分担について話し合う
- 職場の介護支援制度を調べ、利用条件を把握する
- 地域の相談窓口や専門職の連絡先を控えておく
これらは、介護が始まってから慌てて行うよりも、平常時に準備しておく方が圧倒的にスムーズです。
キャリア形成と親の介護は、どちらも人生の大きなテーマです。どちらかを諦めるのではなく、両方を見据えて行動するために、まずは「自分の未来に起こり得ること」を想像することから始めてみてください。