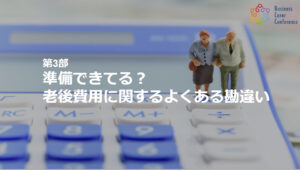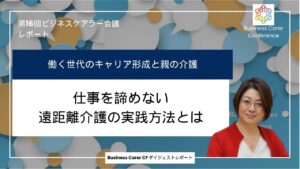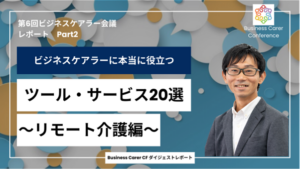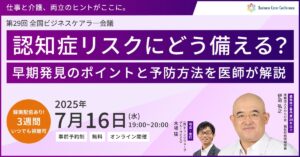仕事と介護の両立をするために「早期発見・早期対応」はどれくらい早く?
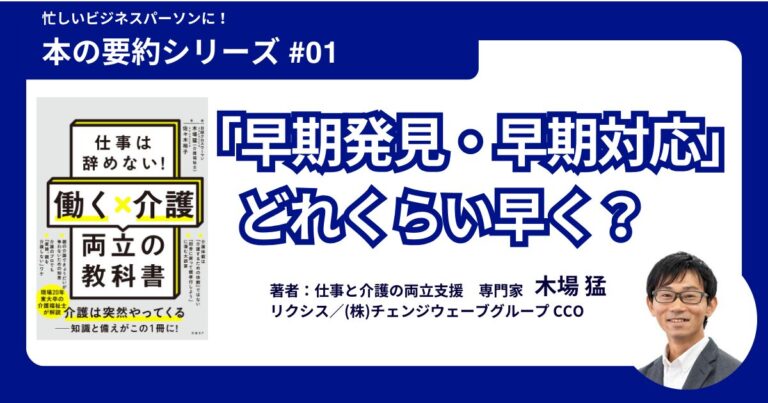
親御さんの様子に変化を感じたとき、皆さんはどう感じるでしょうか?
「このくらいなら大丈夫」と思ってそのままにするのか、あるいは「対応すべき」と考えて早々に行動を起こすのか、判断基準が曖昧なところではあります。
ただ、現状のまま仕事を続ける必要がある方が多いと思われますので、その場合 ”些細な変化であっても” 早期対応が大切です。
今回は、書籍『仕事は辞めない!働く×介護両立の教科書』から「介護保険を利用するタイミング」と「どこに相談するべきか」についてご説明します。
まずは介護についてどれくらい知識があるかをチェック
介護が必要となった場合、介護体制をスムーズに整えるには「介護に対する知識がどれくらいあるのか」で大きな差が生まれます。
では、いざというとき、どのような知識が助けてくれるのでしょうか。
例えば、親御さんが「最近ちょっと生活しづらそう」な段階では、介護保険の申請をしたほうがいいと思いますか?
答えに迷ってしまった方は、次の項目でチェックしてみてください。
「早期発見」「早期対応」とは、どれくらい早く?
介護は「早期発見」「早期対応」が大切です。介護保険を申請し、外部からの支援を受けられる状態なのか、いち早く見極めるようにしたいもの。
介護体制を整えるにあたっては、動き出すまでが1番負担になる部分であり、また人によって差が生じやすいところでもあります。
とはいえ、具体的にどのような状態であれば介護保険の申請をしてもいいのかイメージしづらいですよね。ここで「介護の始まりクイズ」をやってみましょう。
次の8つの状況のうち、介護保険の申請をするべきものはどれか考えてみてください。
1.同じことを何度も繰り返して聞くようになった 2.脳梗塞で寝たきりになった 3.特に病気ではないのに、日中寝込んでいることが増えた 4.常に足腰が痛いと言っている 5.転びやすくなり、先月2回ほど転んだ 6.心臓発作で入院したが、今は回復して生活に支障がない 7.耳が遠くなった 8.最近配偶者が亡くなり、毎日の食事がままならなくなった
答えは、6と7以外すべて申請したほうがいい状態です。
介護保険により要介護認定されるかどうかは、目にみえる病気や障害だけでなく、老化のために起こるさまざまな要因から日常生活を送る上で支障が出ている度合いを考慮して判断されます。
多くの方が抱きがちな要介護認定される条件のイメージとしては「家族では対応できないような介助が必要な状態」なのではないでしょうか。
実はもっと前の段階で、予防として申請することができるのです。
「足腰が痛む」といった年齢的に考えると仕方がないと思われる症状一つとっても、そこには様々な要因が考えられます。そのため要介護認定申請をすることで、筋力を低下させないようリハビリするなど、自立した生活を長く続けられるよう支援する制度もあることを、ぜひ覚えておいてください。
何はともあれ「地域包括支援センター」に相談
ご家族にとって親御さんの介護は初めての経験。どんなサポートをすれば親御さんが快適にはつらつと生活できるのかを判断するのは難しいでしょう。つい、やり過ぎてしまったり、反対にケアが足りずに悪化したりという問題が起こるケースもあります。
プロに任せたほうが状態に合った質の高い介護ができる可能性が高いのです。ではその介護のプロには、どこに行けば相談できるのでしょう。
自分で判断できないと感じたら、まずは「地域包括支援センター」という名前を思い出してください。2005年4月からの介護保険制度の見直しに伴い、地域包括ケアの体制をサポートする機関として位置付けられました。
プロに頼るためには地域包括支援センターが起点となり、要介護認定が必要な状態かどうかを判断し、必要な場合には申請を手助けしてくれます。仮に介護が必要な段階ではないと判断されても、65歳以上の高齢者の方に向けた福祉サービスが各自治体にあり、介護予防のためのサービスや見守りサービスについての提案があります。
また、条件が合わず自治体などのサービスが受けられない場合も、民間の家事代行や見守りなど生活支援の情報を得ることも可能です。
地域包括支援センターは、だいたい中学の学区ごと(人口2万〜3万人)に1カ所を目安に設置されています。
役割は大きくわけて4つ。
| 1.虐待や金銭トラブルから高齢者の方を守る 2.要介護にならないための介護予防サービスの計画を作成 3.65歳以上の方の暮らしに関する相談を受ける 4.地域における介護支援状況の把握や介護支援専門員(ケアマネジャー)の紹介 |
があります。
ちょっとした困りごとでも、まずは相談を

地域包括支援センターは、親御さんの様子についてちょっと困ったことがある方から、たまに親御さんを手伝いにいく状況にある方まで利用できます。
実際に相談してみて現状では特に何もする必要がなかったとしても、「親御さんがそこに住んでいること」をあらかじめ知らせて顔見知りになっておくことで、いざというときに話がスムーズに進みやすくなるのです。
地域包括支援センターが管轄するエリアは地域ごとに決まっているため、親御さんの居住地域で相談してみましょう。親御さんと離れて住んでいる場合は、必ずしも直接訪問せずとも、電話で相談や介護サービスのアレンジをお願いすることができます。
もっと詳しく知りたいという方はこちらの本をチェック!
『仕事は辞めない!働く×介護両立の教科書』では、介護に関する知識を15個の項目に区分し、人によって異なる「介護についての知識量(=介護リテラシー)」に合わせたアドバイスも掲載しています。
15項目はすべて「はい」か「いいえ」で回答する形式です。そのなかには、
・職場の介護制度に関する項目 「あなたは職場の介護に関する制度の詳細について具体的な説明を受けていますか」 ・介護の必要性に関する項目 「在宅介護、施設介護について、どんな状態の場合にどちらを選択すべきかを理解していますか」 ・親御さん自身に関する項目 「親御さんがどのような介護を望んでいるか知っていますか」
などがあります。
状況に合わせた対応をより詳しく知りたい方は、ぜひ書籍を手にとって読んでみてください。
困ったことがあるものの、なかなか動けずにいる方はもちろん、いずれ来るであろう未来に備えて介護リテラシーを高めておきたいという方にも参考にしていただけます。自分が今すべきこと、今後どう対応するべきかが見えてくるはずです。
『仕事は辞めない!働く×介護両立の教科書』
著:木場 猛、佐々木 裕子/編集:日経クロスウーマン
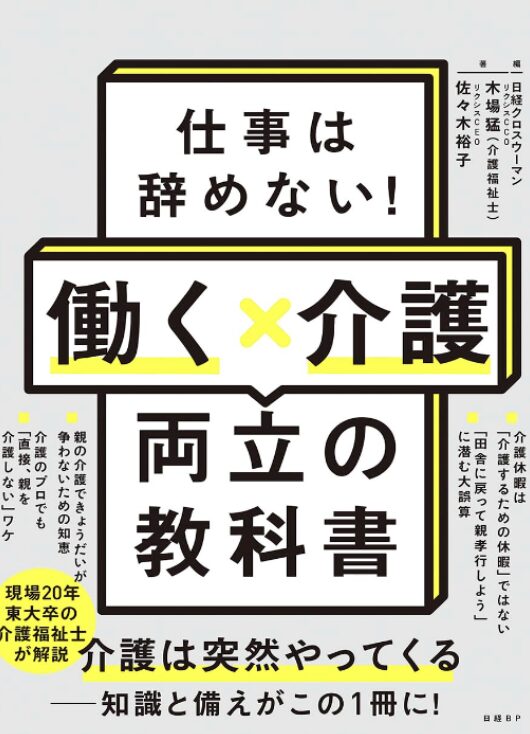
団塊の世代のすべてが後期高齢者となるのが2025年。「大介護時代」はもう始まっています。多くの人が働きながら介護をすることになるなら、必要なのは「休みやすい職場環境」より、むしろ「仕事を休まずに介護をこなすための知識」です。
介護は突然やってきます。そのときになって慌てて無駄に負担を抱えこまないために、親に介護が必要となる前から準備できることは? 「働く」と「介護」を両立させるために誤解してはいけないこととは? 20年間以上介護と仕事の両立を支援してきた東大卒の介護福祉士、木場猛が詳しく解説します。
書籍ご購入ページはこちら
https://amzn.to/4aoYQoS