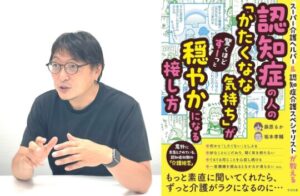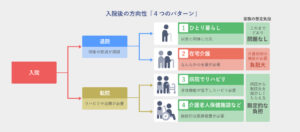見えにくい介護に、見えるサポートを ― 介護中の外出を楽にする「介護マーク」と「思いやり駐車場」

介護中の外出って、本当に大変ですよね。
病院の付き添いや買い物、役所への手続き。必要なことだからやらなきゃいけない。でも、車イスを押しながら、荷物を持って、雨の日なら傘も差して――なんてことになると、心が折れそうになることもあると思います。
そんなときにちょっと楽になるサポートのひとつが「介護マーク」と「思いやり駐車場」です。今回は、日々の小さな困りごとを減らしてくれるこれらのツールを紹介します。
【介護マークとは】「外から見えない介護」のサイン
電車内や駅のエレベーター前で、車イスや杖を使っていないご高齢の親と一緒にいるとき、「元気そうなのに、なぜ優先スペースを使っているの?」といった視線を感じたことはありませんか?
あるいは、認知症の方のように、外見からは介護の必要性がわかりにくい場合には、異性のトイレ介助や下着の購入といった場面で、誤解や偏見にさらされることもあります。
こうした状況に対応するために生まれたのが、「介護マーク」です。
これは、介護していることを周囲に伝えることで、介護する人の心理的な負担をやわらげ、理解と配慮を促すことを目的としたツールです。静岡県で考案され、現在では厚生労働省の後押しのもと、全国への普及が進んでいます。
駅やバス、公共施設、店舗のトイレ、病院の付き添いなど、さまざまな場面でこのマークを身につけることで、周囲の理解や協力を得やすくなるケースが増えています。
また、介護保険サービスを利用している方に対して、ヘルパーが首から介護マークを下げて支援にあたることもあります。このように、介護する人・される人の双方にとって安心感をもたらすツールとしても利用されています。
【介護マークの取得方法】誰でも無料で簡単に手に入れられます
介護マークは、申請書の提出などの手続きは不要で、どなたでも無料で取得することができます。介護中の方の負担を少しでも軽減できるよう、手に取りやすい仕組みになっています。
■ 取得方法
- インターネットからダウンロードして、自宅でプリントアウトし、カードケースなどに入れて使用できます。
- 自治体の高齢介護課や地域包括支援センターなどで配布している地域もあります。「〇〇市 介護マーク」などとインターネットで検索すると、お住まいの地域の配布状況を確認できます。
■ 対象となる方
- 認知症などの症状がある高齢者の介護をされている方
- 障がいのある方の介護をされている方
- その他、介護を必要とする方の支援に携わっている方
■ 費用
- 無料です。
■ 使用上の注意点
- 「介護中であることを周囲に理解してもらう」ことを目的としていますので、それ以外の用途での利用は避けること。
- 使用の必要がなくなった場合は、各自で適切に処分すること。
*参考:大阪市ホームページ https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000639650.html
【思いやり駐車場とは】自治体ごとにマークが異なるが、相互利用が可能
「思いやり駐車場」は、正式には「パーキング・パーミット制度」などと呼ばれ、各自治体がまちづくり条例などに基づいて、スーパーや病院の入り口付近に設置している優先駐車スペースです。高齢者や障がいのある方、妊産婦など、移動に配慮が必要な方々のために設けられています。
■ 駐車スペースの種類と対応
自治体によっては、以下のように区分が設けられています。
- 「車いす利用者優先区画」:車いすでの乗り降りがしやすいよう、幅広に確保されたスペース。
- 「プラスワン区画」:車いすの使用以外にも、介護や妊娠などによって移動に配慮が必要な方が対象のスペース。
ステッカーの種類も、これらの区分ごとに分けて発行されている場合があります。ただし、多くの自治体では「プラスワン区画」が満車の場合、「車いす利用者優先区画」に駐車してもよいといった、柔軟な運用がなされています。
■ 他府県との相互利用も可能
名称やマークは都道府県ごとに異なりますが、原則として他府県で発行された利用証でも利用可能です。マークや制度の違いについては、以下のリンクをご参照ください。
👉広島県ホームページ:思いやり駐車場利用証が利用可能な都道府県一覧(相互利用)
■ 利用できる駐車区画の目印
「思いやり駐車場」であることを示す表示は、以下のいずれかで確認できます。
- 区画の地面に「思いやり駐車場」と記載がある
- 専用のカラーコーンが設置されている
■ 利用証の掲示方法
駐車の際は、発行された利用証を自動車のルームミラーに掲示してください。ルームミラーに掲示することが難しい場合は、フロントガラス付近の外から見える位置であれば問題ありません。
【思いやり駐車場のメリット】「ちょっと便利に」ではなく「より安全に」
「うちの親はまだ歩けるから…」と、思いやり駐車場の利用を遠慮してしまう方も少なくありません。けれども、ほんの少し移動距離を短くするだけで、介助する人の負担も、介護される人の安心感も、大きく変わります。
たとえば、こんな場面があります。
- 雨の日
足元が滑りやすくなる中、転倒のリスクを減らすために、車までの距離が短いことは大きな安心につながります。 - 重い荷物を持っている帰り道
買い物帰りに介助と荷物の両方を抱えるのは、想像以上に大変なこと。近くに車を停められるだけで、安全性が格段に向上します。 - 呼吸器疾患などのあるご高齢の方
少しの移動でも息切れする方にとって、短い距離で済むことは、身体的にも心理的にも負担の軽減になります。
こうした理由から、思いやり駐車場は単なる“便利なスペース”ではありません。それは、介護する人・される人、双方の「安全」を守る手段でもあるのです。
【思いやり駐車場利用カードの取得方法】窓口で申請すれば即日交付
「思いやり駐車証」の利用カードは、各自治体が、対象となる方の身体状況や要介護度に応じて発行しています。
■ 申請方法(多くの自治体の例)
- 多くの自治体では、窓口での即日交付が可能です。必要書類を添えて、申請書に記入するだけで手続きは完了します。
- 郵送で申請できる自治体もあり、返信用封筒を同封すれば、2週間程度で交付されます。手間をかけずに取得できる方法としておすすめです。
▼ 提出書類の例
- 利用申請書
- 該当を証明する書類
・介護が必要な高齢者の場合:介護保険被保険者証
・障害や病気などのある方の場合:障害者手帳、診断書など
- 代理人が申請する場合:代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
■ 費用
- 無料です。発行手数料などはかかりません。
■ 対象となる方(自治体により若干異なります)
- 身体障害、知的障害、精神障害のある方
- 難病患者の方
- 妊産婦の方
- 一時的に歩行が困難な傷病者
- 介護認定を受けた高齢者(多くは要介護1以上)
対象となる障害や傷病には等級や診断書の条件が定められている場合があります。自治体ごとに制度の名称や運用が少しずつ異なりますので、お住まいの市役所や福祉窓口に確認するのが確実です。
【まとめ】ちょっとしたサインが、介護の外出をラクにする
介護は、気力も体力も必要とされる、決して楽ではない営みです。
だからこそ、利用できる制度や支援は、ためらわずに取り入れていくことが大切です。外出のたびに感じる小さなストレスや不安も、適切なサポートを受けることで軽くなることがあります。
それは、介護される方のためだけでなく、介護を続けるあなた自身のための「工夫」でもあります。ご自身をいたわる気持ちで、こうした制度の活用を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
この記事を書いた人

岩瀬 良子(いわせ・りょうこ)
介護支援専門員(ケアマネジャー)・介護福祉士
京都大学卒業後、介護福祉士として、介護老人保健施設・小規模多機能型居宅介護・訪問介護(ヘルパー)の現場に従事。その後、育休中に取得した介護支援専門員の資格を活かし、居宅ケアマネジャーのキャリアを積む。「地域ぐるみの介護」と「納得のいく看取り」を志している。