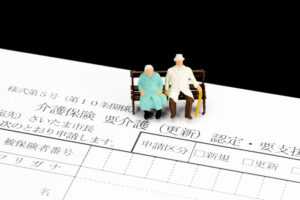もっと身近に、もっと自由に!社会福祉協議会の福祉用具レンタル制度

「介護生活に役立つものがもっと手軽に手に入らないかな?」
――そんな思いを抱いたことのある方は多いのではないでしょうか。
自治体によっては、火災警報器や電磁調理器といった“日常生活用具”を支給したり、高齢の方へタクシーチケットを給付する制度がありますが、そうした給付がない地域でも、より身近で頼れる「貸し出し制度」が存在します。それが「社会福祉協議会によるレンタル事業」です。
全国の自治体にあり、地域に根差した福祉サービスを提供している「社会福祉協議会」(通称「社協(しゃきょう)」)では、車いすや歩行器、介護ベッド、さらには福祉車両などを、介護に必要な用具を必要とする方に貸し出すサービスを行っている場合が多くあります。
「購入するほどではないけれど、少しの間だけ使いたい」「一時的に必要になった」といった方にとって、とても心強い制度です。
今回は、このサービスの概要と利用時の注意点についてご紹介します。
一時的な利用に便利!車いす・杖・歩行器などの貸し出し
各自治体にある「社会福祉協議会」では、福祉用具の貸し出し制度を設けている場合があります。
貸出期間は短期利用が前提で、1ヵ月から半年程度と自治体によって異なります。もちろん、2〜3日などのごく短期間の利用でも可能です。
貸し出される品目は自治体によって異なります。主な貸し出し用具は以下の通りです。
- 車いす
- 杖
- 介護ベッド(電動ベッド)
車いすは多くの自治体で貸し出しが行われていますが、地域によっては、
- ポータブルトイレ
- 入浴用具(シャワーチェア・バスボード)
- 歩行器
- シルバーカー
- スロープ
- 介護ベッド用サイドバー
- 松葉づえ
などを貸し出しているところもあります。
また、使用済みの福祉用具を清掃・整備して再活用するリサイクル事業として実施されている地域もあります。
利用料は基本的に無料なのがうれしいポイント
この制度の魅力は、
- 無料またはごく少額の利用料で借りられる
- 要介護認定・障がい認定を受けていない方でも利用可能
という点です。
多くの社会福祉協議会では、福祉用具の貸し出しを基本的に無料、またはごくわずかな費用で提供しています。特に「まだ介護保険は使えないけれど、ちょっと手助けがほしい」という方には、とてもありがたい仕組みです。
長期的な利用は専門家への相談を
この制度はあくまでも「一時的な利用」が前提です。長期使用を考えている場合には、福祉用具専門相談員や理学療法士などの専門家による適切な選定が重要です。体に合わない用具を長期間使い続けると、逆に身体を痛めてしまうこともあります。
また、すでに介護保険を利用している場合には、介護保険による用具貸与が優先されるケースもあります。
特別なお出かけに!福祉車両の貸し出し
社会福祉協議会では、車椅子やストレッチャーのまま乗車できる福祉車両(リフト付きワゴン車)も、無料で貸し出しを行っていることがあります。ご家族でのドライブや外食の機会にぜひ活用してみてください。
利用にあたってのポイント:
- 運転はご自身やご家族が行う必要があります(普通免許で運転できます)。
- 貸し出しは基本的に無料ですが、燃料代や通行料などの実費は自己負担となります。
- 予約制で台数に限りがあるため、早め(1~2か月前)に問い合わせましょう。
たとえばこんなときに活用できます!
これらの福祉用具や福祉車両は、たとえば以下のようなシーンで役立ちます。
- 長距離の歩行に不安のある家族と旅行や帰省に出かけたいとき
- 高齢の親と地域のイベントや冠婚葬祭などに安心して出かけたいとき
- 骨折や捻挫などで退院後・療養中の一時的なサポートが必要なとき
- 一時的に歩行が不安定になった家族を総合病院に連れて行きたいとき
- 来客や一時的な同居で高齢の親族を自宅に迎えたいとき
まずは「地域名+社協」で検索してみよう
これらのサービスは地域によって内容や条件が異なります。具体的な利用については以下のステップで進めるのがおすすめです。
- まずはお住まいの地域名を入れて、「〇〇市 社協」などで検索してみましょう。
- その地域の社会福祉協議会のホームページで、具体的にどのような用具が貸し出されているかを確認します。(「備品(用具)貸し出し」「福祉機器貸し出し」ほか、「高齢者に関すること」「福祉サービス」「利用したい」などのカテゴリー内にある場合もあります。)
- レンタルを希望する用具があった場合、在庫状況の確認も兼ねて、まずは電話で問い合わせを行います。
- 問い合わせ時の案内に従って、窓口でレンタル申込書の提出などの手続きを進めます。
おわりに
社会福祉協議会は、行政や自治会、民生委員、ボランティアなどと連携しながら、地域福祉の向上に取り組んでいる公共性の高い民間団体です。
介護保険などの制度の狭間にいる方々にも支援が届くよう、全国の自治体に設置され、誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指しています。
福祉用具の貸し出しをはじめとした、生活に寄り添ったさまざまな支援を提供しているため、「困ったときに頼れる場所」として、知っておいて損はありません。
困ったときにはぜひ一度、お住まいの地域の社会福祉協議会に問い合わせてみてください。
この記事を書いた人
岩瀬 良子(いわせ・りょうこ)
介護支援専門員(ケアマネジャー)・介護福祉士
京都大学卒業後、介護福祉士として、介護老人保健施設・小規模多機能型居宅介護・訪問介護(ヘルパー)の現場に従事。その後、育休中に取得した介護支援専門員の資格を活かし、居宅ケアマネジャーのキャリアを積む。「地域ぐるみの介護」と「納得のいく看取り」を志している。