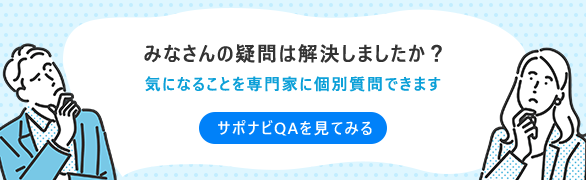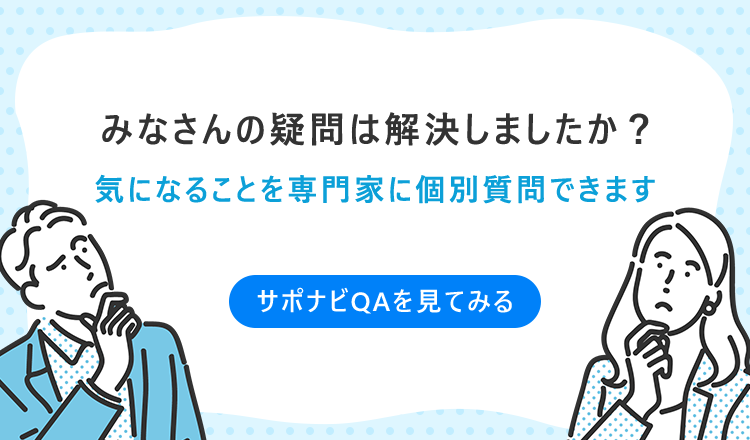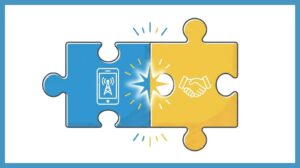高齢者が聞き取りにくいのは高音?それとも低音?(老人性難聴について)

高齢者が聞き取りにくいのは高音
人間は、50代のころから、400Hz以上の高音が聞き取りにくくなります。60代に突入すると、特に会話で用いられる500〜2,000Hzの高音の聞き取り能力が大きく低下します。そして70代を超えてくると、2人に1人は難聴と呼べるような状態になってしまうのです。
これは、内耳(耳の奥のほう)にある感覚細胞や神経線維が劣化してしまうからだと考えられています。特に、こうした高齢化による聴力の機能低下は「老人性難聴」と呼ばれます。女性よりも、男性のほうが、この「老人性難聴」となる可能性が高いようです。
「老人性難聴」が顕著になってくると、他人との会話が嫌になってしまいます。うまく聞き取れず、なんども聞き返すと、恥ずかしい気持ちにもなるからです。
そうなってしまうと、他者との交流が減り、引きこもりがちにもなってしまうでしょう。すると生活不活発病(廃用症候群)になる可能性が高まります。
さらに、そもそも難聴であることは、交通事故などに巻き込まれ、死亡率が高くなることが知られています。また、言葉が聞き取れないと、認知症になるリスクも高まることが指摘されているのです(増田, 2014年)。聞こえないと不便というレベルの話ではないのです。
検査をして補聴器の利用を考えよう
まずは、耳鼻科で検査をしましょう。「老人性難聴」の検査には、純音聴力検査(音の聞き取り能力検査)と語音聴力検査(言葉の聞き取り能力検査)の2つがあります。
まずは、健康診断などでも行われる純音聴力検査です。きちんとしたところだと、小さな防音室で行われることが普通です。左右別々に、だいたい、125〜8,000Hzまでの7段階で聴力が「ピーピー」「ブー」といった音を利用して調べられます。
この純音聴力検査に加えて、語音聴力検査が行われるのは「相手がしゃべっている音は聞こえるが、しゃべっている内容が聞き取れない」ということが起こるからです。
より正確には、語音聴力検査では(1)純音聴力検査の信頼性を確認する(2)難聴の原因を特定する(3)補聴器を利用した場合の効果を予測する、といったことが行われます。
「老人性難聴」は、現在のところ治療法がありません。ですから、医師の診断として、補聴器が有効ということになったら、その指示に従うようにしましょう。それで、生活不活発病、交通事故や認知症のリスクを減らせると考えたら、安いものです。
高齢者と付き合うときの心構えとして
「老人性難聴」は、個人差はありますが、多くの高齢者に共通してみられるものです。ですから、高齢者との付き合いがある人の場合は、背後に「老人性難聴」があることを前提とした会話を心がける必要があります。
基本は「静かな環境で、低めの声で、ゆっくりと」ということになります。ここで、雑音に弱くなるという点については、忘れやすいので注意してください。普段の生活では難聴に困っていても、医師との会話は成立したりするのは、診療所が静かな環境であることが多いからです。
また、補聴器をしている高齢者と、そうでない高齢者は、区別して対応を変えないとなりません。補聴器をしている高齢者であれば、それほど気にしなくても、普通に会話ができたりもします。補聴器があるので、大きな声でしゃべる必要はありません。しかし、ゆっくりしゃべることは、補聴器をしている高齢者からしても助かることが多いようです。
そして当然、補聴器をしていない高齢者との会話のほうが困難になります。補聴器が合わないタイプの「老人性難聴」もあり、その場合は「静かな環境で、低めの声で、ゆっくりと」を、より強く意識する必要があります。どうしても上手く伝わらない場合は、プロの介護職などにしゃべりかたを教わると良いでしょう。
※参考文献
・医療法人/耳鼻咽喉科麻生, 『知っておきたい「老人性難聴」』, 4133(vol.7), 2009年9月1日
・増田 正次, 『高齢者の難聴』, 日本老年医学会雑誌(51巻1号), 2014年1月