1分でわかる「認知症予防のための工夫」
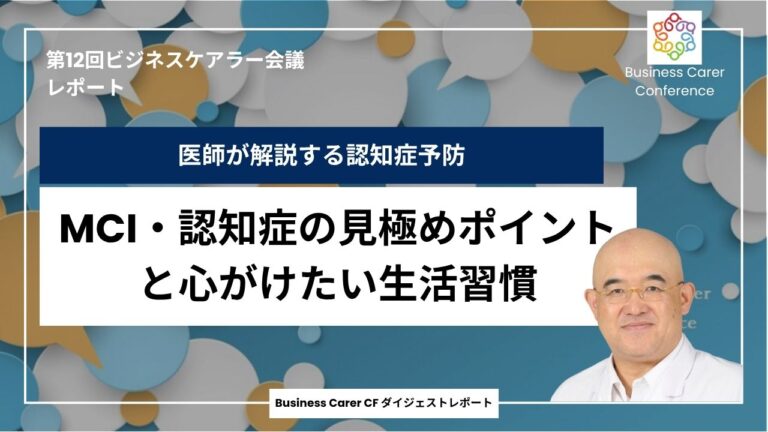
「最近物忘れが増えた気がする」「親の様子が前と違う」—— そんな変化を感じたとき、頭をよぎるのが「認知症」という言葉です。ですが、認知症には段階があり、その一歩手前の状態をMCI(軽度認知障害)と呼びます。
この記事では、MCIと認知症の違い、見極めのヒント、そして日常生活で心がけたい習慣についてまとめます。第12回『全国ビジネスケアラー会議』(2023年12月8日)より
MCIと認知症の違い
認知症は脳の病気で、脳の一部が萎縮し、記憶や判断力が低下していく状態です。進行すると日常生活に人の援助が必要になります。
一方、MCIは記憶や判断力が低下していても、ほとんど援助なしで社会生活を送れる段階です。早期に発見して適切な対策をとれば、改善したり発症を遅らせたりできる可能性があります。
初期に見られやすい2つの症状
認知症の初期症状は大きく分けて2つのタイプがあります。ひとつは「最近の記憶ほどすぐに忘れる」タイプ。たとえば、直前の出来事を覚えていない、同じ質問を繰り返す、物をなくして他人のせいにするなどが見られます。
もうひとつは「ぼーっとする時と普通の時の差が激しい」タイプ。ときに現実にはあり得ないことを信じ込み、妄想や突発的な行動をしてしまうこともあります。
認知機能低下につながる生活習慣
脳への刺激が少ない暮らしは、認知機能の低下を招きやすくなります。特に一人暮らしや夫婦二人きりで会話や活動が少ない場合は注意が必要です。
また、過度なストレスも影響します。環境の急な変化や、頼れる人を失うこともリスクになります。
家族が気をつけたいサインと場面
親が一人暮らしや二人暮らしの場合は、定期的に会話や交流を持つことが大切です。直接会えなくても、電話だけでも刺激になります。
配偶者が入院したり亡くなったりした場合は、生活のリズムが大きく崩れます。早めにヘルパーや通所サービスを検討し、人と関わる機会を増やしましょう。
施設入所で悪化するかは「環境次第」
「施設に入ると認知症が悪化する」と聞くこともありますが、一概には言えません。本人に合う環境と対応があれば、自宅よりも安定する場合もあります。
逆に合わない施設では症状が進むこともあるため、事前の見学や情報収集が重要です。
認知機能維持に効果的な生活習慣
認知症予防には「良い刺激が多い」「ストレスが少ない」生活が効果的です。
具体的には、人との会話、笑うこと、趣味や社会参加、孫やペットとのふれあい、新しいことへの挑戦、旅行や制作、運動と頭を同時に使うコグニサイズなどが挙げられます。
| ①人と会話をするだけでも脳に良い刺激となる
②笑う(血糖値が下がるともいわれている) ③趣味や好きなことをする ④ボランティアなど社会参加する ⑤孫やペットと遊ぶ ⑥読んだり見たりしたものを要約して発表する(人に伝える) ⑦旅行や制作するなどの計画を立てて実行する ⑧新しいことを始める、チャレンジしていく ⑨コグニサイズを意識して行う(cognition:認知機能+exercise:運動=コグニサイズ) ※しりとりをしながら散歩をするなど、運動しながら頭を使う ⑩単純な計算を速く確実にできるように訓練する ⑪体調が悪いなら、それを改善してよい状態に近づける ⑫身体を鍛える、運動を心がける |
ポイントは、本人が自然に取り組める環境を整えることです。「やったほうがいい」と口で言うだけでは続きません。家族や友人が一緒に取り組むことで、習慣化しやすくなります。
認知症やMCIは、早期発見と日々の生活の工夫で進行を遅らせられる可能性があります。気になるサインがあれば、「様子を見る」ではなく、早めに専門医や相談窓口にアクセスしてみましょう。
今日からできる小さな習慣が、未来の自分と家族の安心につながります。






〜認知症の前段階と進行対策〜-アイキャッチ-300x195.jpg)











